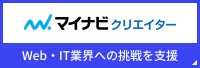発達障害を持ちながら働くことに不安を感じていませんか?転職を考えているけれど、自分に合った職場が見つかるか心配な方も多いでしょう。
この記事では、発達障害の特性を理解し、自分に合った働き方を見つけるための具体的な方法と、活用できる支援サービスについて詳しく解説します。
【まずはチェック!!】求人数の多い大手転職サービスが人気!おすすめの求人数比較表!
大手転職サービスの取り扱い求人件数を独自調査。転職サービスの専任担当者が最新の取り扱い求人情報を確認し、求人数比較表にまとめています。転職活動にあたってはエージェントやサイトを積極的に活用しましょう。まずは一通りサービスを体験してみて自分にあったサービスを見つけることをおすすめします。比較表はこちら。
右にスクロールできます
| おすすめ | リクルートエージェント | マイナビ転職AGENT | doda | リクナビNEXT | パソナキャリア | ビズリーチ | リクルートダイレクトスカウト | マイナビ転職 | エン転職 | JACリクルートメント | type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特色 | 全年代・全業界 | 全業界 | 全年代・全業界 | 全年代・全業界 | ハイクラス・女性向け | ハイクラス全年代・業界 | ハイクラス・全年代 | 全年代・全業界 | 全年代・全業界 | ハイクラス | 全業界・首都圏 |
| 求人数 | 741,460件 | 非公開 | 271,097件 | 1,361,000件以上 | 50,466件 | 182,766件 | 574,714件 | 非公開 | 94,959件 | 47,168件 | 2,746件 |
| 求人の豊富さ | |||||||||||
| ポイント | 非公開求人も多数 | 地方の求人も充実 | エージェント・サイト両方の利用が可能 | 企業からのオファーあり | オファーも受けられる | 2種類のスカウトあり | 登録するとスカウトが多数届く | スカウトサービスあり | 利用者の満足度が高い | コンサルタントのサポートが手厚い | とくにエンジニア、20代、女性の求人に強み |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 |
2026年2月10日調査:各転職エージェントの取り扱い求人件数・各転職サイトの掲載求人数
Contents
発達障害とは?基礎知識を理解しよう
発達障害は、脳の発達の偏りによって生じる特性で、コミュニケーションや行動面で独特の傾向が見られます。決して「できない」ことではなく、「独自の方法でできる」特性を持っているということです。
発達障害の主な特性と分類
発達障害は大きく分けて、ASD(自閉スペクトラム症)、ADHD(注意欠如・多動症)、LD(学習障害)の3つに分類されます。それぞれに異なる特性があり、複数の特性を併せ持つケースも珍しくありません。
ASD(自閉スペクトラム症)の特徴
ASDは、社会的コミュニケーションや対人関係の困難さ、興味や行動の偏りを特徴とする発達障害です。
具体的には、相手の表情や雰囲気から気持ちを読み取ることが苦手だったり、暗黙のルールや「空気を読む」ことに困難を感じたりします。一方で、興味のある分野には深い集中力を発揮し、ルーティンワークや細部への注意が必要な作業を得意とする方が多くいます。
職場では、明確な指示があると理解しやすく、パターン化された業務で高いパフォーマンスを発揮できる傾向があります。また、特定の分野における専門知識を深めることで、その分野のスペシャリストとして活躍する方も少なくありません。
ADHD(注意欠如・多動症)の特徴
ADHDは、不注意、多動性、衝動性という3つの特性を中心とする発達障害です。
不注意の特性では、細かいミスが多い、物をよくなくす、約束を忘れやすいといった傾向が見られます。多動性では、じっとしていられない、落ち着きがないと感じられることがあります。衝動性では、考える前に行動してしまう、順番を待つことが苦手といった特徴があります。
一方で、興味のあることには高い集中力を発揮する「過集中」の状態になることもあります。また、発想力が豊かで、新しいアイデアを生み出すクリエイティブな能力を持つ方も多いです。マルチタスクよりも、一つのことに集中できる環境が適しています。
学習障害(LD)について
学習障害は、知的発達に遅れはないものの、読む、書く、計算するなど特定の学習領域に著しい困難を示す発達障害です。
読字障害(ディスレクシア)では、文字を読むことや文章を理解することに時間がかかります。書字障害(ディスグラフィア)では、文字を書くことや文章をまとめることが苦手です。算数障害(ディスカルキュリア)では、数の概念の理解や計算に困難があります。
これらは特定の領域に限定された困難であり、他の能力は標準的またはそれ以上であることが多いです。適切なツールや方法を活用することで、困難を補いながら仕事をすることが可能です。
発達障害は「個性」として捉える視点
近年、発達障害は「障害」というよりも「脳の個性」として捉える考え方が広がっています。
誰にでも得意なことと苦手なことがありますが、発達障害の方はその差が大きく、特定の領域で顕著に現れるという特徴があります。これは「できないこと」ではなく、「異なる方法でできること」として理解することが重要です。
実際、発達障害の特性を活かして活躍している方は数多くいます。細部へのこだわりを活かした品質管理、集中力を活かしたプログラミング、独創的な発想を活かしたクリエイティブな仕事など、特性に合った環境では高いパフォーマンスを発揮できます。
自分の特性を理解し、それに合った環境や仕事を選ぶことで、発達障害があっても充実したキャリアを築くことができるのです。
発達障害を持つ方が職場で直面する課題
発達障害の方が働く上で、さまざまな困難に直面することがあります。これらの課題を理解することは、対策を考える第一歩となります。
コミュニケーション面での悩み
職場でのコミュニケーションは、発達障害の方が最も困難を感じやすい領域の一つです。
「これ、よろしく」といった曖昧な指示では、何をどこまでやればいいのか分からず困惑してしまいます。また、上司や同僚の表情や雰囲気から「今は忙しそうだから話しかけないほうがいい」といった判断をすることが難しく、タイミングを見計らった声かけに苦労します。
会議や打ち合わせでは、複数の人が同時に話す状況で情報を整理できなかったり、暗黙のルールが分からずに発言のタイミングを逃したりすることもあります。電話対応では、相手の話を聞きながらメモを取る、予期しない質問に即座に対応するといったことにストレスを感じる方も少なくありません。
報告・連絡・相談のタイミングや内容の判断も難しく、報告が遅れたり、逆に些細なことまで報告してしまったりすることがあります。
業務遂行における困難さ
日々の業務遂行においても、発達障害の特性によるさまざまな困難が生じます。
ADHDの特性がある方は、優先順位をつけることが苦手で、重要度の低い業務に時間を取られてしまうことがあります。また、期限の管理が難しく、締め切り直前になって慌てる、あるいは間に合わないといった事態が起こりやすくなります。
複数の業務を同時に進めるマルチタスクは特に困難で、一つの作業から別の作業に切り替える際に大きなエネルギーを消費します。集中が途切れると、元の作業に戻るまでに時間がかかることもあります。
ASDの特性がある方は、業務の手順や方法が変更されたときに対応が難しく、新しいやり方に慣れるまでに時間がかかります。また、予定外の仕事が入ると混乱し、どう対応すればいいか分からなくなることもあります。
細かいミスが多い、確認作業を忘れる、書類の記入漏れがあるといった注意の問題も、仕事の質に影響を与えることがあります。
職場環境への適応の難しさ
物理的な環境や職場の雰囲気への適応も、発達障害の方にとって大きな課題となることがあります。
オープンオフィスのような環境では、周囲の話し声や物音、人の動きなどが気になって集中できないことがあります。感覚過敏がある方は、蛍光灯の明るさ、エアコンの音、特定の匂いなどに敏感に反応し、それが疲労やストレスの原因となります。
職場の暗黙のルールや慣習を理解することも難しく、知らずにマナー違反をしてしまい、人間関係に影響することもあります。休憩時間の雑談や飲み会といった非公式なコミュニケーションの場では、どう振る舞えばいいか分からず、疲れを感じやすくなります。
また、ストレスへの耐性が低く、小さなストレスが積み重なって心身の不調につながりやすい傾向があります。自分の状態を客観的に把握することが難しく、限界を超えてから体調を崩すケースも少なくありません。
転職を成功させるために押さえておきたい3つの鍵
発達障害を持つ方が転職を成功させるためには、自己理解、働き方の選択、サポート体制という3つの要素が重要です。
自己分析:強みと弱みを正確に把握する
転職活動の第一歩は、自分自身を深く理解することです。発達障害の特性を含めて、自分の得意なことと苦手なことを正確に把握することが、適職を見つける鍵となります。
得意なことを洗い出す具体的な方法
得意なことを見つけるには、過去の経験を振り返ることが有効です。
これまでの仕事や学生時代の活動で、「楽しかった」「時間を忘れて取り組めた」「褒められた」経験をリストアップしてみましょう。それらの経験に共通する要素が、あなたの強みのヒントになります。
具体的には、どんな作業が得意か(データ入力、資料作成、分析作業など)、どんな環境で力を発揮できるか(一人で集中できる、ルーティンワーク、明確な指示があるなど)、どんな分野に興味があるか(IT、デザイン、事務作業など)を整理します。
発達障害の特性が強みになることもあります。細部への注意力、パターン認識能力、専門分野への深い知識、独創的な発想力などは、適切な環境で大きな武器となります。
家族や友人、これまでの上司や同僚に「自分の良いところ」を聞いてみるのも、客観的な視点を得る良い方法です。自分では当たり前だと思っていることが、実は貴重な強みであることに気づくかもしれません。
苦手なことを客観的に整理する手順
苦手なことを把握することも同様に重要です。避けるべき環境や業務を明確にすることで、ミスマッチを防げます。
過去の仕事で「ストレスを感じた」「うまくできなかった」「続けることが辛かった」経験を書き出してみましょう。その際、「なぜ苦手だったのか」を具体的に分析することが大切です。
たとえば、「電話対応が苦手」という場合、その理由は何でしょうか。予期しない質問に即答できない、複数の情報を同時に処理できない、相手の声が聞き取りにくい、など具体的な要因を特定します。
苦手なことを「できない」と諦めるのではなく、「どんな工夫や支援があればできるか」を考えることも重要です。たとえば、口頭での指示が苦手なら文書化してもらう、マルチタスクが苦手なら業務の優先順位を明確にしてもらう、といった対策が考えられます。
また、疲れやすい環境や状況(騒がしい場所、長時間の会議、頻繁な予定変更など)も整理しておきましょう。これらの情報は、職場選びや面接での条件交渉に役立ちます。
自己理解を深めるためのツール活用
自己分析をより客観的に行うために、さまざまなツールを活用することができます。
心理検査やアセスメントツールは、自分の特性を数値化・可視化してくれます。WAIS(ウェクスラー成人知能検査)などの知能検査では、得意な認知領域と苦手な領域が明確になります。これらの検査は、医療機関や就労支援機関で受けることができます。
キャリアカウンセリングを受けることも有効です。専門家と対話しながら自己理解を深め、キャリアの方向性を考えることができます。発達障害に理解のあるカウンセラーを選ぶことで、特性を踏まえたアドバイスを得られます。
日々の記録をつけることも、自己理解を深める方法の一つです。どんな業務でストレスを感じたか、どんなときに集中できたか、体調の変化などを記録することで、自分のパターンが見えてきます。
職場体験や実習制度を利用して、実際に働いてみることも貴重な経験です。就労移行支援事業所などでは、さまざまな作業を体験しながら自分に合った仕事を探すことができます。
働き方の選択:3つの雇用形態を知る
発達障害を持つ方の働き方には、大きく分けて3つの選択肢があります。それぞれにメリットとデメリットがあり、自分の状況や希望に合わせて選ぶことが重要です。
一般枠(障がいを開示する働き方)のメリット・デメリット
一般枠で働きながら、発達障害があることを会社に伝える働き方です。
メリットとしては、一般枠の求人数が多く選択肢が広いこと、給与水準が障がい者枠より高い傾向があること、キャリアアップの機会が多いことが挙げられます。また、障がいを開示することで、必要な配慮を受けながら働くことができます。
具体的な配慮の例としては、業務指示を文書化してもらう、静かな環境の席を用意してもらう、定期的な面談で困りごとを相談できる体制を整えてもらう、などがあります。
デメリットとしては、企業によっては発達障害への理解が十分でない場合があること、配慮を受けることに対して周囲の理解が得られにくいことがあること、開示したことで不利益を受ける可能性がゼロではないことなどが考えられます。
この働き方が向いているのは、一定の配慮があれば一般的な業務遂行が可能な方、給与やキャリアを重視したい方、オープンにすることで安心して働きたい方などです。
一般枠(障がいを非開示にする働き方)のメリット・デメリット
一般枠で働き、発達障害があることを会社に伝えない働き方です。
メリットとしては、障がいを理由とした差別や偏見を避けられること、一般の社員と全く同じ条件で働けること、求人の選択肢が最も広いことがあります。
デメリットは、配慮を受けることができないため、すべて自分で対処する必要があること、困難を抱えても相談しにくいこと、ストレスや負担が大きくなりやすいことです。体調を崩したり、パフォーマンスが低下したりしても、その理由を説明できないため、評価に影響する可能性もあります。
また、常に「バレないか」という不安を抱えながら働くことになり、精神的な負担が大きくなることもあります。
この働き方が向いているのは、特別な配慮がなくても業務遂行が可能な方、障がいを開示することに強い抵抗がある方、障がいの影響が比較的軽度な方などです。
障がい者枠で働くメリット・デメリット
障がい者雇用枠での採用となり、障害者手帳が必要です。
メリットとしては、発達障害への理解がある企業で働けること、必要な配慮を前提とした雇用であること、無理のない業務量や内容で働けること、定期的なフォローアップがあることなどが挙げられます。
企業側も障がい者雇用率を達成する必要があるため、積極的に採用を行っており、採用の可能性が高まります。また、ジョブコーチなどの支援者が職場に入ってサポートしてくれる制度もあります。
デメリットとしては、給与水準が一般枠より低い傾向があること、業務内容が限定的になる場合があること、キャリアアップの機会が少ないことなどがあります。また、障害者手帳の取得が必要で、診断書や手続きに時間がかかります。
この働き方が向いているのは、配慮を受けながら安定して働きたい方、無理のないペースで長く働きたい方、発達障害があることをオープンにして働きたい方などです。
自分に合った雇用形態の選び方
どの雇用形態を選ぶかは、自分の状況、価値観、優先順位によって異なります。
まず、自分の障がいの程度を客観的に評価しましょう。配慮がなくても働けるのか、ある程度の配慮があれば働けるのか、しっかりとした支援が必要なのかを判断します。
次に、何を優先するかを考えます。給与やキャリアアップを重視するなら一般枠、安定性や配慮を重視するなら障がい者枠が適しているかもしれません。
また、現在の体調や生活状況も考慮しましょう。体調が不安定な時期は、無理せず障がい者枠から始めて、安定してきたら一般枠への転職を目指すという段階的なアプローチも可能です。
試しに職場実習や短期の仕事を経験してみることで、自分にどの働き方が合っているか見極めることもできます。
最も重要なのは、「自分らしく、長く働き続けられる」選択をすることです。周囲の意見や社会的な期待ではなく、自分自身の実態と希望に基づいて判断しましょう。
サポート体制:利用できる支援機関を把握する
転職活動や就労において、一人で抱え込まずにさまざまな支援を活用することが成功の鍵となります。
公的支援と民間支援の違い
就労支援には、公的機関が提供するものと、民間企業が提供するものがあります。
公的支援機関には、ハローワーク、地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター、発達障害者支援センターなどがあります。これらは無料または低額で利用でき、地域に根ざした支援を提供しています。
公的支援の特徴は、利用者の利益を第一に考えた中立的な立場でのサポート、長期的な関わりが可能なこと、就職後の定着支援も充実していることです。一方で、担当者の専門性にばらつきがあること、手続きに時間がかかることもあります。
民間支援には、転職エージェント、就労移行支援事業所(民間運営の場合)などがあります。民間ならではのスピード感や、専門性の高いサービスが特徴です。
民間支援のメリットは、企業との強いネットワークを持っていること、求人紹介や面接対策など実践的なサポートが充実していること、サービスの質が高いことなどです。デメリットとしては、営利目的のため、必ずしも利用者の最善の利益だけを考えているわけではない場合があることです。
両方を併用することで、それぞれの強みを活かした効果的な支援を受けることができます。
支援機関を選ぶ際のチェックポイント
自分に合った支援機関を選ぶために、いくつかのポイントをチェックしましょう。
まず、発達障害への専門性があるかを確認します。発達障害に理解があり、具体的な支援実績がある機関を選ぶことが重要です。
次に、提供されるサービス内容を確認します。自分が必要としている支援(職業訓練、求人紹介、定着支援など)を提供しているかをチェックしましょう。
アクセスの良さも重要です。定期的に通う必要がある場合、自宅や職場から通いやすい場所にあることが継続のポイントになります。
実際に相談に行ってみて、担当者との相性を確認することも大切です。話しやすい、理解してもらえると感じられるかどうかが、支援の効果に大きく影響します。
また、実績や評判を調べることも有効です。就職率、定着率、利用者の声などを参考にしましょう。
複数の機関を比較検討し、自分に最も合った支援機関を見つけることが、転職成功への近道となります。
発達障害の方が活用できる就労支援サービス
発達障害を持つ方の就労を支援する機関は数多くあります。それぞれの特徴を理解し、自分の状況に合ったサービスを活用しましょう。
就労移行支援:働くための準備とトレーニング
就労移行支援事業所は、一般企業への就職を目指す障がい者に対して、働くために必要な知識やスキルを身につけるための訓練を提供する施設です。
利用できるのは、65歳未満で障害福祉サービス受給者証を持っている方です。利用期間は原則2年間で、週に数日から毎日まで、自分のペースで通うことができます。
提供されるプログラムは多岐にわたります。ビジネスマナーやコミュニケーションスキルの訓練、パソコンスキルや専門的な職業スキルの習得、実際の職場を想定した作業訓練、自己理解を深めるためのプログラム、就職活動のサポート(応募書類作成、面接練習など)などがあります。
特に発達障害の方向けには、自分の特性理解、ストレス対処法、職場での配慮の求め方など、実践的な内容を学べます。模擬職場での実習を通じて、自分の得意・不得意を確認しながら、適職を見つけることができます。
就職後も、職場定着のためのフォローアップ支援が受けられることが大きな特徴です。定期的な面談や、必要に応じた職場訪問などを通じて、長く働き続けるためのサポートを受けられます。
利用料は世帯収入に応じて決まりますが、多くの方は無料または低額で利用できます。
発達障害者支援センター:専門的な相談窓口
発達障害者支援センターは、発達障害児者とその家族を対象とした専門的な相談機関で、都道府県や政令指定都市に設置されています。
このセンターでは、発達障害に関するあらゆる相談に対応しています。就労に関しては、どんな仕事が向いているか、どの支援機関を利用すればいいか、職場での困りごとをどう解決するかなど、具体的なアドバイスを受けられます。
また、就労支援機関との連携も行っており、適切な支援機関への橋渡し役も担っています。地域の資源に精通しているため、自分の状況に合った支援先を紹介してもらえます。
発達障害に関する講演会や研修会、当事者や家族の交流会なども開催されており、情報収集や仲間づくりの場としても活用できます。
利用は無料で、電話や来所での相談が可能です。予約制の場合が多いため、事前に連絡してから訪問しましょう。
地域障害者職業センター:職業リハビリの専門機関
地域障害者職業センターは、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が運営する職業リハビリテーションの専門機関で、全国47都道府県に設置されています。
このセンターの特徴は、職業評価から職業準備訓練、ジョブコーチ支援まで、専門的かつ体系的なサービスを提供していることです。
職業評価では、作業検査や心理検査などを通じて、本人の能力や適性、職業上の課題を詳細に把握します。この結果に基づいて、具体的な職業リハビリテーション計画が作成されます。
職業準備訓練では、実際の職場を想定した環境で、働くために必要なスキルや態度を身につけます。発達障害の方向けには、コミュニケーションスキル、ストレス対処法、作業遂行能力の向上などに焦点を当てた個別プログラムが提供されます。
ジョブコーチ支援(職場適応援助者による支援)は、このセンターの大きな特徴です。就職が決まった後、ジョブコーチが実際の職場に入り、本人と企業の両方をサポートします。業務の教え方、コミュニケーション方法、職場環境の調整など、具体的なアドバイスを提供することで、スムーズな職場適応を支援します。
企業向けのコンサルテーションも行っており、障がい者を雇用する企業への助言や、職場の環境整備の提案なども実施しています。
利用は無料で、ハローワークからの紹介で利用することが一般的です。
障害者就業・生活支援センター:仕事と生活の両面支援
障害者就業・生活支援センターは、障がい者の就業と日常生活の両面を一体的に支援する機関で、全国に設置されています。
このセンターの最大の特徴は、就職活動や職場での問題だけでなく、生活面の課題にも対応してくれることです。仕事と生活は密接に関連しているため、両方を総合的にサポートすることで、安定した就労を実現します。
就業支援としては、就職に向けた準備支援、職場実習のあっせん、求人情報の提供、職場定着のための継続的な支援などを行います。
生活支援としては、生活習慣の形成、健康管理、金銭管理、余暇活動など、日常生活全般の相談に応じます。生活が安定することで、仕事にも良い影響が生まれます。
また、関係機関との連絡調整も重要な役割です。ハローワーク、医療機関、福祉事務所、教育機関など、本人を取り巻くさまざまな機関と連携し、総合的な支援体制を構築します。
発達障害の方の場合、職場での困りごとが生活面のストレスにつながったり、生活リズムの乱れが仕事のパフォーマンスに影響したりすることがあります。このセンターでは、そうした複合的な課題に対して、包括的な視点からサポートを受けられます。
利用は無料で、直接センターに相談することができます。就職前から就職後まで、長期にわたって継続的に利用できることが大きなメリットです。
ハローワーク(公共職業安定所):求人紹介の基本窓口
ハローワークは、国が運営する公共の職業紹介機関で、全国に設置されています。障がい者の就職支援にも力を入れており、専門の窓口が用意されています。
ハローワークには「専門援助部門」があり、障がい者の就職支援を専門に行う職員が配置されています。発達障害についても理解のある担当者が対応してくれます。
提供されるサービスは、求人情報の提供、職業相談、職業紹介、応募書類の作成支援、面接対策、職場実習のあっせん、就職後のフォローアップなど多岐にわたります。
障がい者向けの求人情報は、一般の求人とは別に管理されており、配慮事項や職場環境などの詳細な情報が記載されています。担当者と相談しながら、自分に合った求人を探すことができます。
また、トライアル雇用(試行雇用)制度を利用することもできます。これは、一定期間試験的に働いてから本採用を判断する制度で、企業側も求職者側も、実際に働いてみて相性を確認できるメリットがあります。
ハローワークは全国にあり、利用は無料です。求人数が多く、地域の求人情報が集まっているため、まず最初に相談する窓口として適しています。
転職エージェント:民間の専門サービス
転職エージェントは、民間企業が運営する人材紹介サービスで、近年は障がい者専門のエージェントも増えています。
エージェントが提供する支援の特徴
転職エージェントの最大の特徴は、企業との強いネットワークと、質の高い求人情報を持っていることです。
エージェントは企業の人事担当者と直接やり取りをしており、求人票には載っていない詳細な情報(職場の雰囲気、上司の人柄、配慮の実績など)を持っています。これらの情報は、自分に合った職場を見つける上で非常に貴重です。
また、キャリアアドバイザーによる個別サポートも充実しています。キャリア相談、応募書類の添削、面接対策、給与交渉の代行、入社後のフォローアップなど、転職活動全般をサポートしてくれます。
企業側への条件交渉も行ってくれるため、必要な配慮事項を事前に伝えることができます。自分では言いにくいことも、エージェントを通じて企業に伝えてもらえるのは大きなメリットです。
非公開求人も多く扱っており、ハローワークでは見つからない求人に出会える可能性もあります。
利用は基本的に無料です(求職者側は費用負担なし)。企業側から紹介手数料を受け取るビジネスモデルのため、求職者は無料でサービスを利用できます。
障がい者専門エージェントの選び方
障がい者専門の転職エージェントを選ぶ際には、いくつかのポイントに注意しましょう。
まず、発達障害の支援実績があるかを確認します。身体障がいや精神障がいの支援は行っていても、発達障害への理解や実績が十分でない場合があります。発達障害者の転職支援に特化している、または実績が豊富なエージェントを選びましょう。
取り扱っている求人の質と量も重要です。自分が希望する業種・職種の求人を扱っているか、求人の質(給与、労働条件、配慮の内容など)はどうかを確認しましょう。
キャリアアドバイザーの専門性や相性も大切です。発達障害について理解があり、親身になって相談に乗ってくれるか、実際に面談してみて判断しましょう。
また、入社後のフォロー体制があるかも確認ポイントです。就職がゴールではなく、長く働き続けることが目標なので、定着支援があるエージェントが望ましいです。
複数のエージェントに登録して比較することも有効です。それぞれが持っている求人や提供するサービスが異なるため、併用することでより多くの選択肢を得られます。
代表的な障がい者専門転職エージェントには、アットジーピー、dodaチャレンジ、ランスタッドチャレンジド、マイナビパートナーズ紹介などがあります。
長く安定して働き続けるためのコツ
就職することがゴールではなく、その職場で長く安定して働き続けることが本当の目標です。そのために必要なポイントを押さえておきましょう。
職場定着のための環境調整
職場環境を自分に合ったものに調整することは、長く働くために非常に重要です。
まず、物理的な環境の調整があります。集中しやすい席の配置(壁際、パーテーションで区切られた場所など)、照明の明るさの調整、ノイズキャンセリングヘッドホンの使用許可、整理整頓のためのツールの活用などが考えられます。
業務内容や進め方の調整も重要です。指示は口頭だけでなく文書やメールでももらう、タスクを小分けにして一つずつ取り組む、チェックリストを使って確認漏れを防ぐ、定期的な進捗確認の機会を設けるなどの工夫が効果的です。
コミュニケーション方法の調整も考えましょう。定期的な1on1ミーティングの設定、相談しやすい雰囲気づくり、フィードバックは具体的に伝えてもらう、などです。
これらの調整は、自分から積極的に提案することが大切です。「こうしてもらえると助かる」という具体的な要望を、理由とともに伝えましょう。
合理的配慮の依頼方法
障害者差別解消法により、企業には「合理的配慮」を提供する義務があります。適切に配慮を依頼することで、働きやすい環境を整えることができます。
合理的配慮を依頼する際のポイントは、具体的に伝えることです。「配慮してほしい」だけでは、企業側もどうすればいいか分かりません。「電話対応が苦手なので、できればメール対応を中心にしたい」「マルチタスクが難しいので、業務の優先順位を明確に指示してほしい」など、具体的な内容を伝えましょう。
なぜその配慮が必要なのか、理由も説明します。発達障害の特性とどう関連しているのかを説明することで、理解を得やすくなります。
また、その配慮によってどんな効果が期待できるかも伝えましょう。「この配慮があれば、ミスが減り、生産性が上がります」といった形で、企業側のメリットも示すと良いでしょう。
配慮の依頼は、書面で行うことをお勧めします。口頭だけだと記録が残らず、担当者が変わったときに再度説明が必要になります。メールや文書で残しておくことで、継続的な配慮を受けやすくなります。
配慮は一度依頼したら終わりではありません。働き始めてから新たな課題が見つかることもあります。定期的に見直し、必要に応じて調整を依頼しましょう。
困ったときの相談先を確保する
仕事をしていると、予期しない問題やトラブルに直面することがあります。困ったときにすぐに相談できる先を確保しておくことが、問題の悪化を防ぎます。
職場内の相談先としては、直属の上司、人事部門、産業医・保健師、社内相談窓口などがあります。信頼できる同僚がいれば、日常的な相談相手になってもらえるかもしれません。
職場外の相談先も重要です。就労支援機関(就労移行支援事業所、障害者就業・生活支援センターなど)は、就職後も継続的に相談できます。定期的な面談を設定しておくと、小さな問題のうちに対処できます。
医療機関(主治医、カウンセラー)も大切な相談先です。体調面の不安や服薬の調整など、医療的な視点からのサポートを受けられます。
発達障害者支援センターは、就職後も利用できます。職場での具体的な困りごとについて、発達障害の専門的な視点からアドバイスをもらえます。
家族や友人も、精神的なサポートの重要な存在です。仕事の愚痴を聞いてもらうだけでも、ストレス解消になります。
問題が小さいうちに相談することが重要です。「こんなことで相談していいのかな」と思うようなことでも、早めに相談することで、大きな問題への発展を防げます。
また、定期的に自分の状態をモニタリングし、疲労が蓄積していないか、ストレスサインが出ていないかをチェックする習慣をつけましょう。
みんなが使っている転職サービス上位5選 【1,382人に聞いた転職サービス利用状況】
実際に登録したことのある転職サービスについてアンケートをとりました。アンケート結果として、みんなが使っている転職サービスの上位5サービスは以下です。
- 1位|リクルートエージェント(821人)
- 2位|doda(564人)
- 3位|リクナビNEXT(389人)
- 4位|マイナビ転職AGENT(312人)
- 5位|ビズリーチ(288人)
※転職サービスの利用アンケート(クラウドワークス) 回答数:1,382 / 集計期間:2024年09月19日~10月03日
1位|リクルートエージェント(利用回答数:821人) 圧倒的な求人数
「リクルートエージェント」は、求人数、安定したサービス品質で、まずは登録が必須のエージェントです。
まず何と言っても求人数が多いことがおすすめの理由として挙げられます。転職成功の実績も多く、優れているのは求人の数だけではありません。業界に精通したアドバイザーが在籍しているので、ぴったりの求人を見つけ出してくれます。求人やサービスの質・量ともにトップクラスで転職エージェントとしては定番・王道のサービスです。
営業・技術系を中心にあらゆる業種・職種をカバー。総合型ながら条件ごとに特化したページもあり、使いやすいのも人気の理由です。
- リクルートエージェントのおすすめポイント
- 求人数が圧倒的に多い
- 業界に精通したアドバイザーが在籍
- 条件ごとに特化したページがあり使いやすい
基本データ
| リクルートエージェント | |
|---|---|
| 求人数 | 公開求人数:75万件以上 ※2025年12月2日時点 非公開求人数:35万件以上 ※2025年3月31日時点 |
| 提供サービス | エージェントサービス、提出書類の添削、面接対策、独自に分析した業界・企業情報の提供 |
| 拠点 | 東京・北海道・宮城・宇都宮・さいたま・千葉・横浜・金沢・新潟・長野・静岡・名古屋・京都・大阪・神戸・岡山・広島・高松・福岡 |
| URL | https://www.r-agent.com/ |
2位|doda(利用回答数:564人) エージェント/サイトの一体型で自分でも応募が可能
「doda」は、人材紹介・転職支援を行う大手「パーソルキャリア」が運営する総合型転職サイトです。エージェントサービスも利用できる点が人気の理由の1つになっています。
dodaも求人数が多く、非公開求人も条件が良いものが多いのが大きなポイントです。
また転職サイトと転職エージェントの一体型で、使い方の自由度が高いのもおすすめポイント。エージェントサービスでは専任のキャリアアドバイザーがサポートしてくれます。なお企業との対応は採用プロジェクト担当が行い、求職者と企業とでそれぞれ別のプロフェッショナルが対応します。
- dodaのおすすめポイント
- 非公開求人も好条件多数
- 転職サイトと転職エージェントの一体型で自由度が高い
- 専任のキャリアアドバイザーがサポート、企業は別のプロフェッショナルが対応
基本データ
| doda | |
|---|---|
| 求人数 | 公開求人262,342件/非公開求人31.049件(2024年10月22日現在) |
| 提供サービス | スカウトサービス、年収査定、合格診断、レジュメビルダー、「自己PR」発掘診断、転職タイプ診断、はたらく女性のためのモヤモヤ解消診断、オンライン仕事力診断 |
| 拠点 | 東京・横浜・札幌・仙台・静岡・名古屋・大阪・京都・神戸・岡山・広島・福岡・鹿児島 |
| URL | https://doda.jp/consultant/ |
3位|リクナビNEXT(利用回答数:389人) 求人サイト群の中でも最大級の求人数と使いやすさ
「リクナビNEXT」は大定番の転職サイトで、サイトの見やすさや使いやすさにも定評があります。
エージェントなしの狭義の転職サイトの中では、求人数はトップクラス。新規の求人も多く、定期的にチェックすることで希望に合う求人に出会える可能性が高まります。
ツールが便利でサイトが使いやすいのも特長です。たとえば「気になるリスト」を使うと、気になる企業や後でゆっくりチェックしたい企業をリスト化できるほか、気になるに追加した企業から面接のオファーが来る可能性があります。
そのほか、公開求人・非公開求人の企業からオファーがもらえる「オファーを待つ」、自己分析ツール「グッドポイント診断」などがあります。
- リクナビNEXTのおすすめポイント
- サイトが見やすく使いやすい
- 狭義の転職サイトでは最大級の求人数
- 多くの人が利用している定番の転職サイト
基本データ
| リクナビNEXT | |
|---|---|
| 求人数 | 公開求人824,000件以上(2024年10月22日現在) |
| 提供サービス | オファー、気になるリスト、グッドポイント診断 |
| URL | https://next.rikunabi.com/ |
4位|マイナビ転職AGENT(利用回答数:312人) 20代・30代の求人に強い
「マイナビ転職AGENT」は、さまざまな転職サイトを運営している株式会社マイナビによる転職エージェントです。きめ細かいサポートが受けられると評価されています。
とくに20代・30代の求人が多いので、その世代の人にはおすすめです。また全国に拠点があり地方の求人も充実しているので、大都市圏以外で探している人にもぴったりです。
履歴書や職務経歴書のサポートも充実、初めての転職でも安心して利用できます。IT、営業など業種・職種別のサービスもあります。自分が探している業種と一致するならより探しやすくなるでしょう。
- マイナビ転職AGENTのおすすめポイント
- 20代・30代の求人が多い
- 地方の求人も充実
- 履歴書や職務経歴書のサポートもあり安心
基本データ
| マイナビ転職AGENT | |
|---|---|
| 公開求人数 | 非公開 |
| 提供サービス | エージェントサービス |
| 拠点 | 拠点情報はこちらをご確認ください |
| URL | https://mynavi-agent.jp/ |
5位|ビズリーチ(利用回答数:288人) ハイクラス向けで企業からスカウトが受けられる
「ビズリーチ」は、ハイクラス求人が多いのが特徴の転職サイトです。厳密にはスカウト型のサイトで、エージェントではありません。登録するとヘッドハンターや企業からのスカウトが受けられます。
最大の特長は、ハイクラス求人が多いことです。年収1,000万円以上の求人が1/3以上を占めています。一定以上の経験やスキルがある人が転職活動するのに役立つサービスです。
もう1つの大きな特徴として、登録するだけでヘッドハンターや企業からスカウトが届く点があります。以前は「スカウト」と「プラチナスカウト」の2種がありましたが、今は「プラチナスカウト」に一本化されています。プラチナスカウト経由での採用は全体の約70%。採用される可能性が高く、スカウトが届いたら大きなチャンスです。実際、企業からスカウトが届いた場合は書類選考が免除されます。
基本的にヘッドハンターはアドバイスをしませんが、場合によってはアドバイスをもらえることもあります。無料プランと有料プランがあり、有料プランは制限なく求人に応募できます。
- ビズリーチのおすすめポイント
- ヘッドハンターや企業からのスカウトが受けられるハイクラス向けサイト
- 企業からプラチナスカウトが来た場合は即面接が可能
- 有料プランなら制限なく求人に応募できる
基本データ
| ビズリーチ | |
|---|---|
| 求人数 | 公開求人138,081件(2024年10月22日現在) |
| 提供サービス | スカウトサービス、有料プラン(プレミアムステージ) |
| 拠点 | 東京・大阪・名古屋・福岡・静岡・広島 |
| URL | https://www.bizreach.jp/ |
2026年最新!イチ押しの転職エージェント5選
ここでは、2026年最新のおすすめ転職エージェント5社を厳選してご紹介します。
それぞれの強みや特徴を比較しながら、自分に合ったサービスを見つけ、理想のキャリアへの一歩を踏み出しましょう。
- CAREER-X(キャリア・エックス)
- マイナビクリエイター
- LIG Agent
- Tech-Go(テックゴー)
- エンジニアファクトリー
CAREER-X(キャリア・エックス) 納得のいくキャリアづくりをサポート
「CAREER-X(キャリア・エックス)」は、20代、30代のハイクラス転職に特化した転職エージェントです。
最大の特徴は、納得のいくキャリアを歩むために目の前の転職活動に留まらず、その先のキャリアに伴走すること。キャリアコーチング実績は5,000人以上で、その経験で培ったノウハウをもとに求職者の強みや将来像に合った最適な選択肢をご提案します。
寄り添った面談で強みや挑戦したいことを引き出し、求職者の経験や希望にマッチした求人をご紹介。また、20代で年収700万や30代で経営幹部ポジションなど、ハイクラスの求人や非公開求人も多数保有しています。
また、書類作成と添削、面接対策を内定・入社まで徹底サポート。転職後もフォロー/振り返りを行っており、長期に渡ってキャリアづくりを支援してくれる強い味方です。
- CAREER-X(キャリア・エックス)のおすすめポイント
- ハイクラスの求人や非公開求人も多数保有
- キャリアコーチング実績は5,000人以上
- 長期に渡ってキャリアづくりを支援
基本データ
| CAREER-X(キャリア・エックス) | |
|---|---|
| 求人数 | 非公開 |
| 提供サービス | 職務経歴書の作成と添削、面接対策、入社後フォロー |
| 拠点 | 大阪・福岡 |
| URL | https://career-x.co.jp/ |
マイナビクリエイター 専任のキャリアアドバイザーが直接サポート
「マイナビクリエイター」は、Web・ゲーム・IT業界専門の転職エージェントです。専任のキャリアアドバイザーが個別カウンセリングを行い、求職者のスキルや経験、希望、適性に合った求人をご紹介します。
また、Web・ゲーム・IT業界出身のキャリアアドバイザーが在籍しているのが強みの一つ。企業が求めるクオリティを把握しながら、正確なポートフォリオの作成を徹底サポートします。
さらに、書類添削や面接対策、企業とのやり取り代行も無料で行い、効率よく転職活動ができるよう支援。アドバイザーとのキャリアカウンセリング時間も十分にとれるよう心掛けており、求職者と真摯に向き合う対応力が魅力といえるでしょう。
- マイナビクリエイターのおすすめポイント
- Web・ゲーム・IT業界出身のキャリアアドバイザーが在籍
- 正確なポートフォリオの作成を徹底サポート
- 書類添削や面接対策、企業とのやり取り代行も無料で行う
基本データ
| マイナビクリエイター | |
|---|---|
| 求人数 | 非公開 |
| 提供サービス | 求人紹介、書類添削、面接日程の調整、面接対策、入社日の調整、条件面の交渉、入社日までのフォロー |
| 拠点 | 要確認 |
| URL | https://mynavi-creator.jp |
LIG Agent 活躍の幅を広げる多種多様な求人多数
「LIG Agent」は、クリエイティブ業界で20年の実績を持つ「LIG」が運営するクリエイターのための転職エージェントです。クリエイティブ業界に特化しているからこそ、豊富な知識や最新トレンド、実践的な情報などを惜しみなく提供。
非公開求人を含む多様な業界・職種のクリエイティブ・IT分野の求人を多数保有!求職者の経験やスキル、キャリアステージ、希望の働き方に合った求人をご紹介します。
また、年間1,000名以上のキャリアサポート実績あり。ポートフォリオや職務経歴書の添削、面接対策から入社後のフォローまで一貫して転職活動を徹底的に支援します。
さらに、今後のキャリア設計も一緒に検討してご提案します。クリエイターがスキルと経験を最大限に活かし、理想のキャリアを築ける心強い味方になってくれるはずです。
- LIG Agentのおすすめポイント
- 非公開求人を含む多様な業界・職種の求人を多数保有
- 年間1,000名以上のキャリアサポート実績あり
- 添削、面接対策から入社後のフォローまで一貫してサポート
基本データ
| LIG Agent | |
|---|---|
| 求人数 | 678件(2026年2月17日現在) |
| 提供サービス | キャリア相談、求人紹介、面接対応、書類・ポートフォリオ添削、業界トレンド共有、イベント・セミナー実施 |
| 拠点 | 東京・広島・セブ・ベトナム |
| URL | https://re-new.liginc.co.jp/ |
Tech-Go(テックゴー) エンジニア経験を活かしキャリアアップを実現
「Tech-Go(テックゴー)」は、ITエンジニアの転職支援に特化した転職エージェントです。
ITエンジニア向けの求人を10,000件以上保有。取り扱っている求人は幅広く、「Tech-Go(テックゴー)」だけの独占選考ルートや面接確約求人など、他にはない求人が多数揃っています。
また、現場を知り尽くしたエンジニア業界出身のアドバイザーが在籍しており、選考通過率をアップする書類添削や独自の面接対策など、転職活動を徹底サポートします。
さらに、年収アップを実現する交渉力も強みの一つ。エンジニアとしてキャリアアップを実現し、年収アップを目指している方におすすめの転職エージェントといえます。
- Tech-Go(テックゴー)のおすすめポイント
- ITエンジニア向けの求人を10,000件以上保有
- 現場を知り尽くしたエンジニア業界出身のアドバイザーが在籍
- 年収アップを実現する交渉力も強み
基本データ
| Tech-Go(テックゴー) | |
|---|---|
| 求人数 | 非公開 |
| 提供サービス | 求人紹介、キャリア相談、書類添削、面接対策、日程調整、条件交渉 |
| 拠点 | 東京 |
| URL | https://tech-go.jp/ |
エンジニアファクトリー フリーランスエンジニアの強い味方!
「エンジニアファクトリー」は、18年以上の実績を誇るIT専門フリーランスの転職エージェントです。10,000件以上の求人を保有。会員登録をすれば非公開案件も見ることができ、あなたの経験やスキル、希望にぴったりな求人を見つけることが可能です。
また、年収と再受注率が業界トップクラス!確かな実績があるからこそ、フリーランスとして働いても安心感を得られます。もちろん正社員も対応可能なため、フリーエンジニアとして働いてきた方を、円滑に転職路線に切り替えることができます。
さらに、フリーランス向け福利厚生サービスを設けており、万が一のリスクに備えたサポートが充実している点も魅力の一つです。
- エンジニアファクトリーのおすすめポイント
- 会員登録をすれば非公開求人を見ることができる
- 年収と再受注率が業界トップクラス
- フリーランス向け福利厚生サービスが充実している
基本データ
| エンジニアファクトリー | |
|---|---|
| 求人数 | 12,450件(2026年2月17日現在) |
| 提供サービス | 案件紹介、企業面談、企業との契約 |
| 拠点 | 東京・大阪 |
| URL | https://www.engineer-factory.com/ |
まとめ:自分らしく働ける職場を見つけよう
発達障害を持ちながら働くことは、確かに課題もありますが、適切な理解と支援があれば、十分に実現可能です。
この記事で紹介したように、まずは自分自身の特性を深く理解することが第一歩です。得意なことと苦手なことを把握し、どんな環境で力を発揮できるかを知ることで、自分に合った職場を見つけやすくなります。
働き方の選択肢は一つではありません。一般雇用枠(開示・非開示)、障がい者雇用枠それぞれにメリット・デメリットがあり、自分の状況や価値観に合わせて選ぶことができます。最初は障がい者枠で安定を優先し、慣れてきたら一般枠を目指すといった段階的なアプローチも可能です。
そして、一人で抱え込まずに、さまざまな支援サービスを活用しましょう。就労移行支援事業所、発達障害者支援センター、地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター、ハローワーク、転職エージェントなど、多くの専門機関があなたの就労をサポートしてくれます。
就職後も、継続的なフォローアップと環境調整が重要です。困ったときにすぐ相談できる体制を整え、必要な配慮を適切に依頼しながら、長く安定して働き続けることを目指しましょう。
発達障害は「障害」である以前に、あなたの「個性」です。その個性を理解し、活かせる環境を見つけることで、充実したキャリアを築くことができます。
転職活動は一歩を踏み出す勇気が必要ですが、適切な準備と支援があれば、必ず自分らしく働ける職場が見つかります。この記事が、あなたの転職活動の一助となれば幸いです。







.png)


.png)