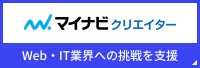「何度確認しても不安が消えない」「同じ行動を繰り返してしまい仕事が進まない」――強迫性障害(OCD)を抱えながら働く方の多くが、こうした悩みを抱えています。しかし、適切な理解と対処法を知ることで、症状と上手に付き合いながら充実したキャリアを築くことは十分に可能です。
本記事では、強迫性障害の基礎知識から、適職の選び方、職場での具体的な対処法、休職・復職のステップ、そして利用できる支援制度まで、働く上で必要な情報を網羅的に解説します。
【まずはチェック!!】求人数の多い大手転職サービスが人気!おすすめの求人数比較表!
大手転職サービスの取り扱い求人件数を独自調査。転職サービスの専任担当者が最新の取り扱い求人情報を確認し、求人数比較表にまとめています。転職活動にあたってはエージェントやサイトを積極的に活用しましょう。まずは一通りサービスを体験してみて自分にあったサービスを見つけることをおすすめします。比較表はこちら。
右にスクロールできます
| おすすめ | リクルートエージェント | マイナビ転職AGENT | doda | リクナビNEXT | パソナキャリア | ビズリーチ | リクルートダイレクトスカウト | マイナビ転職 | エン転職 | JACリクルートメント | type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特色 | 全年代・全業界 | 全業界 | 全年代・全業界 | 全年代・全業界 | ハイクラス・女性向け | ハイクラス全年代・業界 | ハイクラス・全年代 | 全年代・全業界 | 全年代・全業界 | ハイクラス | 全業界・首都圏 |
| 求人数 | 741,460件 | 非公開 | 271,097件 | 1,361,000件以上 | 50,466件 | 182,766件 | 574,714件 | 非公開 | 94,959件 | 47,168件 | 2,746件 |
| 求人の豊富さ | |||||||||||
| ポイント | 非公開求人も多数 | 地方の求人も充実 | エージェント・サイト両方の利用が可能 | 企業からのオファーあり | オファーも受けられる | 2種類のスカウトあり | 登録するとスカウトが多数届く | スカウトサービスあり | 利用者の満足度が高い | コンサルタントのサポートが手厚い | とくにエンジニア、20代、女性の求人に強み |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 |
2026年2月10日調査:各転職エージェントの取り扱い求人件数・各転職サイトの掲載求人数
Contents
強迫性障害は適切な職場環境選びが大切
強迫性障害があっても、自分に合った職場環境を選び、適切な対策を講じることで、長く安定して働き続けることができます。大切なのは、症状の特性を理解し、それに応じた職種選びや働き方の工夫を行うことです。
まず押さえておきたいのは、強迫性障害は「気合いで乗り越えるもの」ではなく、医学的な治療が必要な疾患であるということ。無理に症状を抑え込もうとするのではなく、医療機関での治療を受けながら、自分の症状特性に合った環境を選ぶことが重要です。
強迫性障害の基本的な理解
強迫性障害について正しく理解することは、適切な対処法を見つける第一歩です。ここでは、病気の特徴や主な症状について詳しく見ていきましょう。
強迫性障害とはどのような精神疾患か
強迫性障害(Obsessive-Compulsive Disorder: OCD)は、本人の意思に反して不安や恐怖を伴う考えが繰り返し浮かび、それを打ち消すために特定の行動を繰り返してしまう精神疾患です。
日本における有病率は約2〜3%とされ、決して珍しい病気ではありません。多くの場合、10代後半から20代前半に発症しますが、社会人になってから症状が顕在化するケースも少なくありません。
重要なのは、これは単なる「心配性」や「几帳面な性格」とは異なり、脳内の神経伝達物質のバランスが関係している医学的な疾患だということです。適切な治療によって症状をコントロールすることが可能であり、多くの方が日常生活や仕事との両立を実現しています。
主な症状①:繰り返し浮かぶ不安や恐怖
強迫性障害の中核症状の一つが「強迫観念」です。これは、本人が不合理だと分かっていても、繰り返し頭に浮かんでくる不安や恐怖、イメージのことを指します。
代表的な強迫観念には以下のようなものがあります。
不潔恐怖・汚染恐怖:「手が汚れているのではないか」「病原菌がついているのではないか」という不安が常につきまとう。職場では、ドアノブや共用のパソコンに触れることに強い抵抗を感じることがあります。
確認強迫:「鍵をかけ忘れたのではないか」「メールの送信先を間違えたのではないか」という不安が消えず、何度も確認してしまう。業務上のミスへの過度な不安から、提出物のチェックに膨大な時間がかかることもあります。
加害恐怖:「自分が誰かを傷つけてしまうのではないか」という不安。例えば、会議中に「暴言を吐いてしまうのではないか」という考えが浮かんで集中できなくなることがあります。
対称性・完璧性へのこだわり:「物が左右対称でないと気が済まない」「完璧にできないなら意味がない」という思考。デスク周りの配置や書類の並べ方に過度にこだわり、本来の業務が進まなくなることがあります。
これらの不安は、理屈では不合理だと分かっていても、強い不快感や恐怖を伴うため、無視することが非常に困難です。
主な症状②:止められない反復行動
強迫観念によって引き起こされる不安を和らげるために行う反復的な行動を「強迫行為」といいます。一時的には不安が軽減されますが、根本的な解決にはならず、むしろ症状を悪化させる悪循環に陥ることが特徴です。
洗浄・清潔行為:手洗いを何十回も繰り返す、シャワーに何時間もかかる、消毒を過度に行う。職場でもトイレから戻るたびに長時間手を洗い続け、周囲から不審に思われることがあります。
確認行為:鍵やガスの元栓を何度も確認する、送信したメールを繰り返しチェックする、作成した資料を何十回も見直す。この確認行為によって、退社時間が大幅に遅れたり、業務の進捗が著しく遅れたりすることがあります。
儀式的行為:特定の順序や回数で動作を行わないと気が済まない。例えば、パソコンの起動手順を決められた順番で行う、特定の数字を避けるために動作を繰り返すなど。
順序へのこだわり:物の配置や作業の手順が決まった通りでないと強い不安を感じる。予期せぬ業務変更や急な依頼に対応できず、パニックになることがあります。
強迫行為は短期的には不安を軽減しますが、長期的には「この行為をしないと不安が解消されない」という思い込みを強化し、症状を慢性化させてしまいます。
職場生活における強迫性障害の困りごと
強迫性障害は、職場生活においてさまざまな困難をもたらします。しかし、正しい理解と適切な対処によって、これらの困難は軽減可能です。
適切な治療を受ければ就労継続は十分可能
「強迫性障害があると仕事を続けられないのでは」という不安を持つ方は少なくありませんが、実際には適切な治療とサポートを得ることで多くの方が安定して就労を継続しています。
重要なのは、症状を完全にゼロにすることを目指すのではなく、「症状があっても日常生活や仕事に大きな支障がない状態」を目指すことです。多くの方が、症状とうまく付き合いながら、充実したキャリアを築いています。
業務効率や対人関係への具体的な影響
強迫性障害が職場生活に与える影響は、症状のタイプや重症度によって異なりますが、以下のような困難が生じやすくなります。
業務遂行上の困難
作業の遅延:確認強迫がある場合、メールの送信前に何度もチェックする、報告書を何十回も見直すなど、通常の何倍もの時間がかかることがあります。結果として納期に間に合わなかったり、残業が常態化したりします。
優先順位の混乱:完璧性へのこだわりから、重要度の低い作業にも過度に時間をかけてしまい、本来優先すべき業務が後回しになることがあります。
集中力の低下:強迫観念が頭の中で繰り返され、目の前の業務に集中できなくなります。会議中も強迫観念に囚われて、議論の内容が頭に入ってこないことがあります。
対人関係上の困難
コミュニケーションの回避:加害恐怖がある場合、「失礼なことを言ってしまうのでは」という不安から、必要なコミュニケーションすら避けてしまうことがあります。
チームワークの難しさ:順序や方法へのこだわりが強い場合、他者と協力して柔軟に業務を進めることが困難になります。
誤解を受けやすい:症状による行動が周囲に理解されず、「仕事が遅い」「協調性がない」「変わった人」といった誤解を受けることがあります。
遅刻や欠勤のリスク:朝の準備に強迫行為が絡む場合、家を出るまでに異常に時間がかかり、遅刻や欠勤につながることがあります。
これらの困難は個人の努力だけで解決することは難しく、医療的な治療とともに、職場での理解と配慮が必要になります。
強迫性障害の特性に合った職種とは
自分の症状特性に合った職種を選ぶことは、長く安定して働くための重要なポイントです。ここでは、強迫性障害のある方に適した職場環境の特徴と、具体的な職種例を紹介します。
マイペースで作業できる業務が基本
強迫性障害のある方にとって、自分のペースで業務を進められる環境は非常に重要です。確認行為や儀式的行為に時間がかかる場合でも、柔軟に時間配分を調整できる職種が適しています。
個人作業が中心の業務:常にチームで動く必要がなく、ある程度独立して作業を進められる職種は、自分のペースを保ちやすくなります。納期はあっても、作業の進め方や時間配分を自分で決められる業務が理想的です。
ノルマや時間的プレッシャーが少ない職場:分刻みのスケジュールや厳しいノルマがあると、強迫行為を行う時間が取れず、不安が高まり症状が悪化しやすくなります。ある程度余裕を持ったスケジュールで業務を進められる環境を選びましょう。
タスクを細分化できる業務:大きなプロジェクトよりも、明確に区切られた小さなタスクを積み重ねる業務の方が、達成感を得やすく、完璧主義による負担も軽減されます。
繰り返しの作業や定型業務:ある程度パターン化された業務は、予測可能性が高く、不安を感じにくいという利点があります。ただし、単調すぎて飽きてしまわないよう、適度な変化があることも重要です。
人間関係のストレスが少ない環境を選ぶ
対人関係でのストレスは、強迫症状を悪化させる大きな要因の一つです。必要以上に対人接触が多い職場は避け、適度な距離感を保てる環境を選ぶことが大切です。
少人数の職場:大規模な組織よりも、少人数のチームや部署の方が、人間関係がシンプルで、周囲の理解も得やすい傾向があります。
対面接客が少ない業務:不特定多数の顧客と接する接客業は、加害恐怖や社交不安がある場合、大きなストレス源となります。顧客対応があっても、メールやチャットなど非対面のコミュニケーションが中心の業務が適しています。
急な対応が少ない職場:突発的なクレーム対応や、予測できない状況への即時対応が求められる職場は、不安を高めやすくなります。ある程度予測可能で、準備時間が取れる業務が望ましいでしょう。
時間や場所に縛られない働き方ができる職場
柔軟な勤務形態が認められている職場は、症状に合わせた働き方の調整がしやすく、長期的な就労継続につながります。
リモートワークが可能:在宅勤務ができれば、通勤による疲労やストレスが軽減されます。また、自宅という安心できる環境で、必要に応じて強迫行為を行いながら業務を進めることができます。
フレックスタイム制度:出勤時間を柔軟に設定できれば、朝の強迫行為に時間がかかっても、遅刻を気にせず出勤できます。また、通勤ラッシュを避けることで、ストレスを軽減できます。
時短勤務や週休3日制:フルタイム勤務が難しい場合、時短勤務や週休3日などの選択肢があると、治療と仕事の両立がしやすくなります。
副業やフリーランス:複数の収入源を持つことで、一つの仕事に過度に依存せず、症状の波に応じて働き方を調整できます。
具体的におすすめの職種例
以下は、強迫性障害のある方が比較的働きやすいとされる職種の例です。ただし、個人の症状や適性によって向き不向きは異なるため、あくまで参考として考えてください。クローズ就労で利用できる特化型転職エージェントも併せてご紹介します。
IT・プログラミング関連:プログラマー、Webデザイナー、システムエンジニアなど。個人作業が中心で、リモートワークも普及しており、柔軟な働き方がしやすい分野です。細部へのこだわりが強みになることもあります。
IT特化型エージェント:Tech-Go(テックゴー)、UZUZ(ウズウズ)
データ入力・事務作業:定型的な作業が中心で、自分のペースで進められます。正確性が求められる業務では、確認する傾向が適切に活かされることもあります。
ライター・編集者:自宅での作業が可能で、締め切りはあっても作業時間の配分は自由です。文章へのこだわりが質の高い成果物につながります。
イラストレーター・デザイナー:創作活動が中心で、対人ストレスが少なめです。細部へのこだわりが作品のクオリティを高めることもあります。
図書館司書・アーカイブ管理:静かな環境で、整理整頓や分類作業が中心。秩序へのこだわりが業務に活かせます。
研究職・分析業務:じっくりと一つのテーマに取り組める環境。詳細な検証や分析作業では、慎重さが強みになります。
翻訳者:個人作業が中心で、在宅での仕事も可能。言葉の正確性へのこだわりが高品質な翻訳につながります。
経理・会計業務:数字の正確性が重要な業務では、確認の丁寧さが評価されることがあります。ルーチンワークが多く、予測可能性が高い点も利点です。
経理特化型転職エージェント:ジャスネットキャリア
避けた方が良い職種の特徴
一方で、以下のような特徴を持つ職種は、強迫性障害のある方にとってストレスが大きく、症状悪化のリスクが高いため、慎重に検討する必要があります。
時間的プレッシャーが強い職種:救急医療、消防士、報道関係など、瞬時の判断や迅速な対応が常に求められる職種は、確認行為を行う時間的余裕がなく、強い不安を引き起こします。
対人接触が頻繁な職種:販売員、飲食店スタッフ、コールセンターなど、不特定多数の人と頻繁に接する職種は、加害恐怖や社交不安がある場合、大きなストレス源となります。
衛生に配慮が必要な環境での作業:清掃業、介護職、医療職など、衛生面での配慮が必要な職種は、不潔恐怖がある場合、症状を著しく悪化させる可能性があります。
変化や予測不可能性が高い職種:営業職、イベント企画、クレーム対応など、状況が常に変化し、予測が困難な職種は、不安を高めやすくなります。
マルチタスクが必須の職種:複数の業務を同時並行で進める必要がある職種は、優先順位の判断が難しく、パニックに陥りやすくなります。
責任が重すぎる職種:人命に関わる業務や、大きな金額を扱う業務など、ミスが許されない環境は、確認強迫を悪化させやすくなります。
ただし、これらはあくまで一般的な傾向であり、適切な治療と職場の配慮があれば、どのような職種でも働くことは可能です。自分の症状の程度や治療の進捗状況を考慮して判断しましょう。
働き続けるために必要な5つの対策
強迫性障害を抱えながら長く働き続けるためには、医療的な治療と並行して、日常生活や職場での対策を講じることが重要です。
早期受診が症状悪化を防ぐカギ
強迫性障害の症状に気づいたら、できるだけ早く精神科や心療内科を受診することが、その後の経過を大きく左右します。
早期受診のメリット
症状が軽いうちに治療を始めれば、比較的短期間で改善が期待できます。症状が慢性化・重症化してからでは、治療に時間がかかり、日常生活への影響も大きくなります。
また、早期に診断がつくことで、自分の困難が病気によるものだと理解でき、「自分の性格が悪いのでは」「努力が足りないのでは」という自責感から解放されます。この理解は、適切な対処法を見つける出発点となります。
受診のタイミング
以下のような状態が2週間以上続いている場合は、受診を検討しましょう。
- 強迫観念や強迫行為のために1日1時間以上を費やしている
- 業務や日常生活に明らかな支障が出ている
- 症状による苦痛が強く、生活の質が低下している
- 症状のために遅刻や欠勤が増えている
治療は自己判断で中断せず継続することが重要
強迫性障害の治療において最も大切なのは、継続性です。症状が改善したと感じても、自己判断で治療を中断すると、再発のリスクが高まります。
日々の生活習慣で症状をコントロールする方法
治療と並行して、日常生活の中で症状をコントロールするためのセルフケアを実践することも重要です。
- 規則正しい生活リズム
- 適度な運動
- バランスの取れた食事
- アルコール・カフェインの制限
- リラクゼーション技法
上記の習慣を実践して、安定した状態を保つよう心がけましょう。
職場での合理的配慮を求める
障害者雇用促進法により、企業には障害のある労働者に対して合理的配慮を提供する義務があります。これは、障害者手帳の有無にかかわらず適用されます。
合理的配慮の具体例
強迫性障害のある方に対する合理的配慮には、以下のようなものがあります。
- 始業時刻の柔軟化(フレックスタイム制の適用)
- 在宅勤務やテレワークの許可
- 業務量の調整や納期の柔軟化
- 確認作業に十分な時間を確保できるスケジュール設定
- 静かな作業環境の提供(個室や間仕切りのある席など)
- 通院のための休暇取得への配慮
- 業務内容の調整(過度にプレッシャーのかかる業務の軽減)
職場への開示について
病気のことを職場に開示するかどうかは、個人の判断です。開示することで必要な配慮を受けられる一方、偏見のリスクもゼロではありません。信頼できる上司や人事担当者と相談しながら、慎重に判断しましょう。
開示する場合も、すべての同僚に伝える必要はありません。業務上必要な範囲で、最小限の人に伝えることも可能です。
信頼できる相談相手を持つ
一人で抱え込まず、信頼できる相談相手を持つことは、長期的な就労継続において非常に重要です。
- 主治医
- 産業医・保健師
- 家族や友人
- 同じ悩みを持つ仲間
- 専門の相談機関
上記のような人たちに相談することで、客観的なアドバイスが得られるでしょう。
強迫性障害のある方向けの就労支援サービス
転職や再就職を考える際、障害者手帳の有無にかかわらず、さまざまな就労支援サービスを利用することができます。
障害を開示する・しないの選択肢
就職活動において、強迫性障害のことを開示するかどうかは重要な判断です。それぞれにメリットとデメリットがあります。
オープン就労(障害を開示して働く)
メリット
- 必要な配慮を受けやすい
- 症状への理解が得られやすく、通院などもしやすい
- 障害者雇用枠を利用でき、雇用が安定しやすい
- 無理に症状を隠す必要がなく、精神的な負担が少ない
デメリット
- 職種や業務内容が限定される場合がある
- 給与水準が一般雇用より低い場合がある
- 偏見や差別のリスクがゼロではない
クローズ就労(障害を開示せずに働く)
メリット
- 職種の選択肢が広い
- 一般雇用と同じ条件で働ける
- キャリアアップの機会が多い
デメリット
- 必要な配慮を受けにくい
- 症状を隠すストレスがある
- 通院などの調整が難しい場合がある
- 症状悪化時のサポートが受けにくい
どちらを選ぶべきか
症状が軽度で、治療が安定しており、配慮なしでも働ける場合は、クローズ就労も選択肢となります。一方、定期的な通院が必要な場合や、業務上の配慮が必要な場合は、オープン就労の方が長期的には安定して働きやすいでしょう。
また、「最初はクローズで始めて、必要に応じて後から開示する」という段階的なアプローチも可能です。自分の症状の程度、治療の状況、キャリアプランなどを総合的に考えて判断しましょう。
転職エージェントの活用
転職活動において、専門の転職エージェントを利用することで、効率的に自分に合った職場を見つけることができます。
障害者雇用専門の転職エージェント
障害者雇用枠での就職を希望する場合、障害者雇用に特化した転職エージェントがあります。これらのエージェントは、企業側も障害への理解があり、配慮が前提となっている求人を扱っています。
主なサービス内容:
- キャリアカウンセリング
- 症状に合った求人の紹介
- 企業との条件交渉
- 面接対策や書類添削
- 入社後のフォローアップ
代表的なエージェント:dodaチャレンジ、atGP、ランスタッドチャレンジドなど
一般の転職エージェント
クローズ就労を希望する場合は、一般の転職エージェントを利用します。この場合、病気のことは開示せずに転職活動を進めることになります。
リモートワークや柔軟な勤務形態を希望条件として伝えることで、結果的に症状に合った職場を見つけられることもあります。
エージェント利用のポイント
- 複数のエージェントに登録し、比較検討する
- 自分の症状や希望する働き方を正直に伝える(オープン就労の場合)
- 焦らず、じっくりと自分に合った職場を探す
- 内定後も、条件面で不明な点は遠慮なく確認する
障害のある方向けの転職サービスについては、以下の記事が参考になります。
- 「障害者向けおすすめ転職エージェント12選!条件別のおすすめもご紹介」
- 「適応障害のある方向けのおすすめ転職エージェント15選!特徴も比較・解説」
- 「ADHDの方におすすめの転職エージェント17選!オープン向け、クローズもOKの両方をご紹介」
- 「発達障害者向けおすすめ転職エージェント12+3選!オープン・クローズ・グレーゾーンすべて解説」
ハローワークの専門窓口
公共職業安定所(ハローワーク)には、障害のある方の就職を支援する専門窓口があります。
専門援助窓口
各ハローワークに設置されている専門援助窓口では、障害のある方の就職相談や職業紹介を行っています。精神障害者雇用トータルサポーターという専門の相談員が配置されており、精神疾患についての理解があります。
主なサービス
- 就職相談とキャリアカウンセリング
- 求人情報の提供と紹介
- 職業訓練の案内
- 障害者トライアル雇用の活用
- 企業との調整
障害者雇用枠での就職という選択肢
障害者雇用促進法により、従業員が一定数以上の企業には、障害者を雇用する義務があります。この制度を活用することで、配慮のある環境で働くことができます。
障害者雇用枠の特徴
企業側の理解:障害者雇用枠で採用される場合、企業側は障害があることを前提として雇用します。そのため、必要な配慮を受けやすい環境が整っています。
雇用の安定性:法定雇用率の達成が企業の義務であるため、雇用が比較的安定しています。
段階的なキャリア形成:最初は配慮のある環境で経験を積み、症状が安定してきたら、徐々に業務の幅を広げることも可能です。
障害者手帳がない場合の対応
障害者雇用枠を利用するには、原則として障害者手帳が必要です。しかし手帳がなくても、以下のような選択肢があります。
一般雇用で配慮を依頼:手帳がなくても、診断書をもとに企業に配慮を依頼することは可能です。合理的配慮の提供は、手帳の有無にかかわらず企業の義務とされています。
手帳取得を検討:症状が一定の基準を満たす場合、精神障害者保健福祉手帳の取得を検討することもできます。手帳があることで、障害者雇用枠だけでなく、税制上の優遇や公共交通機関の割引などのメリットもあります。
みんなが使っている転職サービス上位5選 【1,382人に聞いた転職サービス利用状況】
実際に登録したことのある転職サービスについてアンケートをとりました。アンケート結果として、みんなが使っている転職サービスの上位5サービスは以下です。
- 1位|リクルートエージェント(821人)
- 2位|doda(564人)
- 3位|リクナビNEXT(389人)
- 4位|マイナビ転職AGENT(312人)
- 5位|ビズリーチ(288人)
※転職サービスの利用アンケート(クラウドワークス) 回答数:1,382 / 集計期間:2024年09月19日~10月03日
1位|リクルートエージェント(利用回答数:821人) 圧倒的な求人数
「リクルートエージェント」は、求人数、安定したサービス品質で、まずは登録が必須のエージェントです。
まず何と言っても求人数が多いことがおすすめの理由として挙げられます。転職成功の実績も多く、優れているのは求人の数だけではありません。業界に精通したアドバイザーが在籍しているので、ぴったりの求人を見つけ出してくれます。求人やサービスの質・量ともにトップクラスで転職エージェントとしては定番・王道のサービスです。
営業・技術系を中心にあらゆる業種・職種をカバー。総合型ながら条件ごとに特化したページもあり、使いやすいのも人気の理由です。
- リクルートエージェントのおすすめポイント
- 求人数が圧倒的に多い
- 業界に精通したアドバイザーが在籍
- 条件ごとに特化したページがあり使いやすい
基本データ
| リクルートエージェント | |
|---|---|
| 求人数 | 公開求人数:75万件以上 ※2025年12月2日時点 非公開求人数:35万件以上 ※2025年3月31日時点 |
| 提供サービス | エージェントサービス、提出書類の添削、面接対策、独自に分析した業界・企業情報の提供 |
| 拠点 | 東京・北海道・宮城・宇都宮・さいたま・千葉・横浜・金沢・新潟・長野・静岡・名古屋・京都・大阪・神戸・岡山・広島・高松・福岡 |
| URL | https://www.r-agent.com/ |
2位|doda(利用回答数:564人) エージェント/サイトの一体型で自分でも応募が可能
「doda」は、人材紹介・転職支援を行う大手「パーソルキャリア」が運営する総合型転職サイトです。エージェントサービスも利用できる点が人気の理由の1つになっています。
dodaも求人数が多く、非公開求人も条件が良いものが多いのが大きなポイントです。
また転職サイトと転職エージェントの一体型で、使い方の自由度が高いのもおすすめポイント。エージェントサービスでは専任のキャリアアドバイザーがサポートしてくれます。なお企業との対応は採用プロジェクト担当が行い、求職者と企業とでそれぞれ別のプロフェッショナルが対応します。
- dodaのおすすめポイント
- 非公開求人も好条件多数
- 転職サイトと転職エージェントの一体型で自由度が高い
- 専任のキャリアアドバイザーがサポート、企業は別のプロフェッショナルが対応
基本データ
| doda | |
|---|---|
| 求人数 | 公開求人262,342件/非公開求人31.049件(2024年10月22日現在) |
| 提供サービス | スカウトサービス、年収査定、合格診断、レジュメビルダー、「自己PR」発掘診断、転職タイプ診断、はたらく女性のためのモヤモヤ解消診断、オンライン仕事力診断 |
| 拠点 | 東京・横浜・札幌・仙台・静岡・名古屋・大阪・京都・神戸・岡山・広島・福岡・鹿児島 |
| URL | https://doda.jp/consultant/ |
3位|リクナビNEXT(利用回答数:389人) 求人サイト群の中でも最大級の求人数と使いやすさ
「リクナビNEXT」は大定番の転職サイトで、サイトの見やすさや使いやすさにも定評があります。
エージェントなしの狭義の転職サイトの中では、求人数はトップクラス。新規の求人も多く、定期的にチェックすることで希望に合う求人に出会える可能性が高まります。
ツールが便利でサイトが使いやすいのも特長です。たとえば「気になるリスト」を使うと、気になる企業や後でゆっくりチェックしたい企業をリスト化できるほか、気になるに追加した企業から面接のオファーが来る可能性があります。
そのほか、公開求人・非公開求人の企業からオファーがもらえる「オファーを待つ」、自己分析ツール「グッドポイント診断」などがあります。
- リクナビNEXTのおすすめポイント
- サイトが見やすく使いやすい
- 狭義の転職サイトでは最大級の求人数
- 多くの人が利用している定番の転職サイト
基本データ
| リクナビNEXT | |
|---|---|
| 求人数 | 公開求人824,000件以上(2024年10月22日現在) |
| 提供サービス | オファー、気になるリスト、グッドポイント診断 |
| URL | https://next.rikunabi.com/ |
4位|マイナビ転職AGENT(利用回答数:312人) 20代・30代の求人に強い
「マイナビ転職AGENT」は、さまざまな転職サイトを運営している株式会社マイナビによる転職エージェントです。きめ細かいサポートが受けられると評価されています。
とくに20代・30代の求人が多いので、その世代の人にはおすすめです。また全国に拠点があり地方の求人も充実しているので、大都市圏以外で探している人にもぴったりです。
履歴書や職務経歴書のサポートも充実、初めての転職でも安心して利用できます。IT、営業など業種・職種別のサービスもあります。自分が探している業種と一致するならより探しやすくなるでしょう。
- マイナビ転職AGENTのおすすめポイント
- 20代・30代の求人が多い
- 地方の求人も充実
- 履歴書や職務経歴書のサポートもあり安心
基本データ
| マイナビ転職AGENT | |
|---|---|
| 公開求人数 | 非公開 |
| 提供サービス | エージェントサービス |
| 拠点 | 拠点情報はこちらをご確認ください |
| URL | https://mynavi-agent.jp/ |
5位|ビズリーチ(利用回答数:288人) ハイクラス向けで企業からスカウトが受けられる
「ビズリーチ」は、ハイクラス求人が多いのが特徴の転職サイトです。厳密にはスカウト型のサイトで、エージェントではありません。登録するとヘッドハンターや企業からのスカウトが受けられます。
最大の特長は、ハイクラス求人が多いことです。年収1,000万円以上の求人が1/3以上を占めています。一定以上の経験やスキルがある人が転職活動するのに役立つサービスです。
もう1つの大きな特徴として、登録するだけでヘッドハンターや企業からスカウトが届く点があります。以前は「スカウト」と「プラチナスカウト」の2種がありましたが、今は「プラチナスカウト」に一本化されています。プラチナスカウト経由での採用は全体の約70%。採用される可能性が高く、スカウトが届いたら大きなチャンスです。実際、企業からスカウトが届いた場合は書類選考が免除されます。
基本的にヘッドハンターはアドバイスをしませんが、場合によってはアドバイスをもらえることもあります。無料プランと有料プランがあり、有料プランは制限なく求人に応募できます。
- ビズリーチのおすすめポイント
- ヘッドハンターや企業からのスカウトが受けられるハイクラス向けサイト
- 企業からプラチナスカウトが来た場合は即面接が可能
- 有料プランなら制限なく求人に応募できる
基本データ
| ビズリーチ | |
|---|---|
| 求人数 | 公開求人138,081件(2024年10月22日現在) |
| 提供サービス | スカウトサービス、有料プラン(プレミアムステージ) |
| 拠点 | 東京・大阪・名古屋・福岡・静岡・広島 |
| URL | https://www.bizreach.jp/ |
2026年最新!イチ押しの転職エージェント5選
ここでは、2026年最新のおすすめ転職エージェント5社を厳選してご紹介します。
それぞれの強みや特徴を比較しながら、自分に合ったサービスを見つけ、理想のキャリアへの一歩を踏み出しましょう。
- CAREER-X(キャリア・エックス)
- マイナビクリエイター
- LIG Agent
- Tech-Go(テックゴー)
- エンジニアファクトリー
CAREER-X(キャリア・エックス) 納得のいくキャリアづくりをサポート
「CAREER-X(キャリア・エックス)」は、20代、30代のハイクラス転職に特化した転職エージェントです。
最大の特徴は、納得のいくキャリアを歩むために目の前の転職活動に留まらず、その先のキャリアに伴走すること。キャリアコーチング実績は5,000人以上で、その経験で培ったノウハウをもとに求職者の強みや将来像に合った最適な選択肢をご提案します。
寄り添った面談で強みや挑戦したいことを引き出し、求職者の経験や希望にマッチした求人をご紹介。また、20代で年収700万や30代で経営幹部ポジションなど、ハイクラスの求人や非公開求人も多数保有しています。
また、書類作成と添削、面接対策を内定・入社まで徹底サポート。転職後もフォロー/振り返りを行っており、長期に渡ってキャリアづくりを支援してくれる強い味方です。
- CAREER-X(キャリア・エックス)のおすすめポイント
- ハイクラスの求人や非公開求人も多数保有
- キャリアコーチング実績は5,000人以上
- 長期に渡ってキャリアづくりを支援
基本データ
| CAREER-X(キャリア・エックス) | |
|---|---|
| 求人数 | 非公開 |
| 提供サービス | 職務経歴書の作成と添削、面接対策、入社後フォロー |
| 拠点 | 大阪・福岡 |
| URL | https://career-x.co.jp/ |
マイナビクリエイター 専任のキャリアアドバイザーが直接サポート
「マイナビクリエイター」は、Web・ゲーム・IT業界専門の転職エージェントです。専任のキャリアアドバイザーが個別カウンセリングを行い、求職者のスキルや経験、希望、適性に合った求人をご紹介します。
また、Web・ゲーム・IT業界出身のキャリアアドバイザーが在籍しているのが強みの一つ。企業が求めるクオリティを把握しながら、正確なポートフォリオの作成を徹底サポートします。
さらに、書類添削や面接対策、企業とのやり取り代行も無料で行い、効率よく転職活動ができるよう支援。アドバイザーとのキャリアカウンセリング時間も十分にとれるよう心掛けており、求職者と真摯に向き合う対応力が魅力といえるでしょう。
- マイナビクリエイターのおすすめポイント
- Web・ゲーム・IT業界出身のキャリアアドバイザーが在籍
- 正確なポートフォリオの作成を徹底サポート
- 書類添削や面接対策、企業とのやり取り代行も無料で行う
基本データ
| マイナビクリエイター | |
|---|---|
| 求人数 | 非公開 |
| 提供サービス | 求人紹介、書類添削、面接日程の調整、面接対策、入社日の調整、条件面の交渉、入社日までのフォロー |
| 拠点 | 要確認 |
| URL | https://mynavi-creator.jp |
LIG Agent 活躍の幅を広げる多種多様な求人多数
「LIG Agent」は、クリエイティブ業界で20年の実績を持つ「LIG」が運営するクリエイターのための転職エージェントです。クリエイティブ業界に特化しているからこそ、豊富な知識や最新トレンド、実践的な情報などを惜しみなく提供。
非公開求人を含む多様な業界・職種のクリエイティブ・IT分野の求人を多数保有!求職者の経験やスキル、キャリアステージ、希望の働き方に合った求人をご紹介します。
また、年間1,000名以上のキャリアサポート実績あり。ポートフォリオや職務経歴書の添削、面接対策から入社後のフォローまで一貫して転職活動を徹底的に支援します。
さらに、今後のキャリア設計も一緒に検討してご提案します。クリエイターがスキルと経験を最大限に活かし、理想のキャリアを築ける心強い味方になってくれるはずです。
- LIG Agentのおすすめポイント
- 非公開求人を含む多様な業界・職種の求人を多数保有
- 年間1,000名以上のキャリアサポート実績あり
- 添削、面接対策から入社後のフォローまで一貫してサポート
基本データ
| LIG Agent | |
|---|---|
| 求人数 | 678件(2026年2月17日現在) |
| 提供サービス | キャリア相談、求人紹介、面接対応、書類・ポートフォリオ添削、業界トレンド共有、イベント・セミナー実施 |
| 拠点 | 東京・広島・セブ・ベトナム |
| URL | https://re-new.liginc.co.jp/ |
Tech-Go(テックゴー) エンジニア経験を活かしキャリアアップを実現
「Tech-Go(テックゴー)」は、ITエンジニアの転職支援に特化した転職エージェントです。
ITエンジニア向けの求人を10,000件以上保有。取り扱っている求人は幅広く、「Tech-Go(テックゴー)」だけの独占選考ルートや面接確約求人など、他にはない求人が多数揃っています。
また、現場を知り尽くしたエンジニア業界出身のアドバイザーが在籍しており、選考通過率をアップする書類添削や独自の面接対策など、転職活動を徹底サポートします。
さらに、年収アップを実現する交渉力も強みの一つ。エンジニアとしてキャリアアップを実現し、年収アップを目指している方におすすめの転職エージェントといえます。
- Tech-Go(テックゴー)のおすすめポイント
- ITエンジニア向けの求人を10,000件以上保有
- 現場を知り尽くしたエンジニア業界出身のアドバイザーが在籍
- 年収アップを実現する交渉力も強み
基本データ
| Tech-Go(テックゴー) | |
|---|---|
| 求人数 | 非公開 |
| 提供サービス | 求人紹介、キャリア相談、書類添削、面接対策、日程調整、条件交渉 |
| 拠点 | 東京 |
| URL | https://tech-go.jp/ |
エンジニアファクトリー フリーランスエンジニアの強い味方!
「エンジニアファクトリー」は、18年以上の実績を誇るIT専門フリーランスの転職エージェントです。10,000件以上の求人を保有。会員登録をすれば非公開案件も見ることができ、あなたの経験やスキル、希望にぴったりな求人を見つけることが可能です。
また、年収と再受注率が業界トップクラス!確かな実績があるからこそ、フリーランスとして働いても安心感を得られます。もちろん正社員も対応可能なため、フリーエンジニアとして働いてきた方を、円滑に転職路線に切り替えることができます。
さらに、フリーランス向け福利厚生サービスを設けており、万が一のリスクに備えたサポートが充実している点も魅力の一つです。
- エンジニアファクトリーのおすすめポイント
- 会員登録をすれば非公開求人を見ることができる
- 年収と再受注率が業界トップクラス
- フリーランス向け福利厚生サービスが充実している
基本データ
| エンジニアファクトリー | |
|---|---|
| 求人数 | 12,450件(2026年2月17日現在) |
| 提供サービス | 案件紹介、企業面談、企業との契約 |
| 拠点 | 東京・大阪 |
| URL | https://www.engineer-factory.com/ |
まとめ:強迫性障害と向き合いながら働くために
強迫性障害を抱えながら働くことは決して容易ではありませんが、適切な理解と対処法、そして周囲のサポートがあれば、十分に可能です。
最も重要なのは、強迫性障害が「性格の問題」ではなく、医学的な治療が必要な疾患であると理解することです。無理に症状を抑え込もうとするのではなく、医療機関での治療を受けながら、自分の症状特性に合った働き方を見つけることが大切です。
強迫性障害があっても、自分らしく働き、充実したキャリアを築くことは可能です。この記事が、そのための一助となれば幸いです。







.png)


.png)