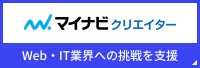「障害があるけれど、手帳は持っていない」「手帳を取るべきか迷っている」そんな悩みを抱えている方は少なくありません。障害者雇用という言葉を聞いたことがあっても、実際に手帳がないと応募できないのか、どんな選択肢があるのか、わからないことも多いでしょう。
この記事では、障害者雇用と手帳の関係について詳しく解説し、手帳なしでできることや手帳取得を検討する際のポイントをわかりやすくお伝えします。自分に合った働き方を見つけるための第一歩として、ぜひ参考にしてください。
【まずはチェック!!】求人数の多い大手転職サービスが人気!おすすめの求人数比較表!
大手転職サービスの取り扱い求人件数を独自調査。転職サービスの専任担当者が最新の取り扱い求人情報を確認し、求人数比較表にまとめています。転職活動にあたってはエージェントやサイトを積極的に活用しましょう。まずは一通りサービスを体験してみて自分にあったサービスを見つけることをおすすめします。比較表はこちら。
右にスクロールできます
| おすすめ | リクルートエージェント | マイナビ転職AGENT | doda | リクナビNEXT | パソナキャリア | ビズリーチ | リクルートダイレクトスカウト | マイナビ転職 | エン転職 | JACリクルートメント | type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特色 | 全年代・全業界 | 全業界 | 全年代・全業界 | 全年代・全業界 | ハイクラス・女性向け | ハイクラス全年代・業界 | ハイクラス・全年代 | 全年代・全業界 | 全年代・全業界 | ハイクラス | 全業界・首都圏 |
| 求人数 | 741,460件 | 非公開 | 271,097件 | 1,361,000件以上 | 50,466件 | 182,766件 | 574,714件 | 非公開 | 94,959件 | 47,168件 | 2,746件 |
| 求人の豊富さ | |||||||||||
| ポイント | 非公開求人も多数 | 地方の求人も充実 | エージェント・サイト両方の利用が可能 | 企業からのオファーあり | オファーも受けられる | 2種類のスカウトあり | 登録するとスカウトが多数届く | スカウトサービスあり | 利用者の満足度が高い | コンサルタントのサポートが手厚い | とくにエンジニア、20代、女性の求人に強み |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 |
2026年2月10日調査:各転職エージェントの取り扱い求人件数・各転職サイトの掲載求人数
Contents
手帳なしで障害者雇用枠への応募は可能?
障害者雇用枠での就職を考えたとき、多くの方が最初に気になるのが「手帳がなくても応募できるのか」という点です。結論から言うと、障害者雇用枠に応募するためには、原則として障害者手帳の所持が必要です。
障害者雇用の応募要件と手帳の関係
障害者雇用促進法に基づく障害者雇用制度では、企業が法定雇用率を達成するために雇用する「障害者」の定義が明確に定められています。この定義に該当するためには、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかを所持していることが条件となります。
企業が障害者雇用枠で採用する際、ハローワークへの報告や助成金の申請などの手続きにおいて、手帳番号の記載が求められます。そのため、手帳を持っていない方は、制度上「障害者」としてカウントされず、障害者雇用枠での採用対象とはなりません。
診断書がある場合や障害があることが明らかな場合でも、手帳がなければ障害者雇用枠での応募はできないという点には注意が必要です。医師の診断だけでは、法律上の「障害者」として認められないのです。
手帳がない場合に選べる就職ルート
では、手帳を持っていない方は就職の選択肢がないのかというと、そうではありません。手帳がない場合でも、以下のような就職ルートがあります。
一般雇用枠での応募
最も一般的な選択肢は、一般雇用枠での就職活動です。手帳の有無に関わらず、誰でも応募できる求人に対して、自分の能力やスキルをアピールして採用を目指します。この場合、障害があることを開示するかどうかは本人の判断に委ねられます。
開示しない場合は、他の応募者と同じ条件で選考を受けることになります。開示する場合は、企業の理解を得た上で、必要な配慮について相談しながら働くことが可能です。ただし、一般雇用枠では障害者雇用枠のような法的な配慮義務はないため、企業によって対応は異なります。
就労移行支援の活用
手帳がなくても、自治体の判断で就労移行支援事業所を利用できるケースがあります。就労移行支援では、就職に向けたトレーニングや企業とのマッチング支援を受けられます。利用中に手帳取得を検討することもできるため、就職準備と並行して選択肢を広げることができます。
トライアル雇用の利用
ハローワークが実施する障害者トライアル雇用制度は、手帳を持っている方が対象ですが、一般のトライアル雇用制度であれば手帳なしでも利用可能です。この制度を通じて、実際に働きながら自分の適性を確認し、企業との相性を見極めることができます。
障害者雇用制度の基礎知識をわかりやすく整理
障害者雇用について理解を深めるために、まずは制度の基本的な仕組みを押さえておきましょう。制度の目的や企業の義務を知ることで、自分がどのような立場で就職活動を進めるべきか判断しやすくなります。
企業が守るべき雇用義務率の仕組み
障害者雇用促進法では、一定規模以上の企業に対して、従業員の一定割合以上を障害者として雇用することを義務付けています。これを「法定雇用率」と呼びます。
2024年4月現在、民間企業の法定雇用率は2.5%と定められています。つまり、従業員が40人以上いる企業は、少なくとも1人以上の障害者を雇用する必要があるということです。この雇用率は段階的に引き上げられており、2026年7月には2.7%に引き上げられる予定です。
法定雇用率を達成できていない企業には、不足する障害者数に応じて「障害者雇用納付金」の納付義務が課されます。従業員100人超の企業では、不足1人あたり月額5万円が徴収されるため、企業にとっては大きな負担となります。
一方で、法定雇用率を超えて障害者を雇用している企業には、「障害者雇用調整金」や各種助成金が支給されます。このように、制度には企業が積極的に障害者雇用に取り組むインセンティブが組み込まれています。
一般採用枠との主な違いとは
障害者雇用枠と一般雇用枠には、いくつかの重要な違いがあります。これらの違いを理解することで、自分にとってどちらの枠が適しているか判断する材料になります。
選考プロセスの違い
一般雇用枠では、学歴や職歴、スキルなどが重視され、多くの応募者の中から選考が行われます。一方、障害者雇用枠では、業務遂行能力だけでなく、障害の特性と業務内容の適合性、必要な配慮の実現可能性なども考慮されます。
障害者雇用枠では、書類選考や面接に加えて、実際の業務を体験する職場実習や、支援機関を交えた三者面談が実施されることもあります。企業側も、長期的に安定して働いてもらうことを重視するため、選考に時間をかける傾向があります。
配慮の有無
最も大きな違いは、合理的配慮の提供に関する法的義務の有無です。障害者雇用枠で採用された場合、企業には障害者差別解消法に基づく合理的配慮の提供義務があります。これは、障害のある従業員が能力を発揮できるよう、過度な負担にならない範囲で必要な調整を行うことを求めるものです。
一般雇用枠で障害を開示して働く場合も配慮を受けられることはありますが、法的義務ではないため、企業の裁量に委ねられる部分が大きくなります。
給与や待遇
障害者雇用枠だからといって、必ずしも給与が低いわけではありません。職種や企業、本人のスキルによって待遇は大きく異なります。ただし、短時間勤務や業務内容の調整がある場合、結果的に給与水準が一般雇用枠より低くなることはあります。
近年では、障害者雇用枠でも正社員採用や、一般雇用枠と同等の待遇を提供する企業が増えています。特に専門性の高い職種では、能力に応じた評価と処遇が行われるケースも多くなっています。
障害者雇用で働くことの利点と課題
障害者雇用枠での就職を検討する際には、メリットとデメリットの両面を理解しておくことが大切です。自分の状況や価値観に照らして、どちらが自分に合っているか考えてみましょう。
手帳を持って働く主な利点
配慮を受けながら安定して働ける
障害者雇用枠で働く最大のメリットは、法的に保障された配慮を受けられることです。勤務時間の調整、業務内容の配分、通院への配慮、職場環境の整備など、自分の障害特性に応じた支援を企業に求めることができます。
例えば、精神障害のある方であれば、体調に波があることを前提に、繁忙期の業務量調整や定期的な面談の実施などを相談できます。発達障害のある方なら、マルチタスクを避けた業務設計や、静かな作業環境の確保などを依頼できるでしょう。
こうした配慮があることで、無理なく長期的に働き続けられる可能性が高まります。一般雇用枠で障害を隠して働く場合と比べて、心理的な負担も軽減されます。
支援機関のサポートを受けられる
障害者雇用では、就労移行支援事業所や就労定着支援、障害者就業・生活支援センターなど、様々な支援機関のサポートを受けながら働くことができます。これらの機関は、職場での困りごとや人間関係の悩みについて相談に乗ってくれたり、企業との間に入って調整してくれたりします。
特に就職して間もない時期や、環境の変化があったときには、第三者の支援があることで大きな安心感につながります。一人で抱え込まず、専門家の助けを借りられる体制があることは、働き続ける上で重要な支えとなります。
企業の理解が得られやすい
障害者雇用枠で採用する企業は、あらかじめ障害のある社員を受け入れる準備と覚悟ができています。障害者雇用の担当部署や担当者が配置されていることも多く、相談しやすい環境が整っています。
また、法定雇用率達成のために障害者雇用に取り組んでいる企業では、障害のある社員が長く働けるよう、積極的に環境整備を進めているところも増えています。障害への理解がある環境で働けることは、精神的な安定につながります。
キャリアアップの機会も
近年では、障害者雇用でスタートしても、能力や実績に応じてキャリアアップできる企業が増えています。最初は契約社員やアルバイトとして入社し、段階的に業務範囲を広げながら、正社員登用を目指すというルートも一般的になってきました。
特にIT系の専門職や事務系の企画職などでは、障害の有無に関わらず、スキルと成果で評価される文化が定着しつつあります。
事前に知っておきたい注意点
求人の選択肢が限られる場合がある
障害者雇用枠の求人は、一般雇用枠と比べると数が限られています。特に地方や専門性の高い職種では、希望に合う求人が見つかりにくいこともあります。
また、企業によっては、障害者雇用枠の業務内容が定型的な補助業務に限定されているケースもあります。自分のキャリアビジョンと照らし合わせて、その業務内容で満足できるかを慎重に検討する必要があります。
障害者雇用枠の求人を効率よくチェックするためには、障害者特化型の転職エージェントを利用するのがおすすめです。具体的には、「dodaチャレンジ」「atGP」「障害者雇用バンク」などの転職エージェントがあり、1人ひとりに合わせたサポートを提供しています。
以下の記事では、障害者特化型の転職エージェントについてサービスごとに解説しています。
LITALICO仕事ナビ/dodaチャレンジ/ランスタッドチャレンジド/atGP/障害者雇用バンク
給与水準が一般より低いケースも
障害者雇用枠での採用では、短時間勤務や業務内容の配慮により、結果的に給与が一般雇用枠より低くなることがあります。特に最初は時給制や契約社員からのスタートとなる企業も多く、すぐに高収入を得ることは難しい場合があります。
ただし、これは企業や職種によって大きく異なります。正社員として一般と同等の待遇で採用する企業もあれば、段階的に昇給や正社員登用を行う企業もあります。応募前に待遇面をしっかり確認することが大切です。
「障害者」として見られることへの抵抗感
障害者雇用枠で働くということは、職場で「障害のある社員」として認識されることを意味します。これに対して、心理的な抵抗や葛藤を感じる方もいます。
自分のアイデンティティとして障害をどう捉えるか、どこまで開示するかは、非常に個人的な問題です。障害者雇用を選ぶ前に、自分の気持ちと向き合い、納得した上で決断することが重要です。
配慮の程度は企業によって差がある
法律で合理的配慮が義務付けられているとはいえ、その具体的な内容や質は企業によって大きく異なります。障害者雇用に積極的に取り組み、ノウハウを蓄積している企業もあれば、法定雇用率を満たすために最低限の対応しかしていない企業もあります。
求人票だけでは配慮の質は判断しにくいため、面接や職場見学の機会を利用して、実際の職場環境や企業の姿勢を確認することが大切です。
障害者手帳の取得で変わる選択肢と支援内容
障害者手帳を取得すると、障害者雇用枠への応募が可能になるだけでなく、様々な支援制度やサービスを利用できるようになります。手帳取得を検討している方は、どんな選択肢が広がるのかを知っておくとよいでしょう。
手帳があることで利用できる就労サポート
就労移行支援の利用
就労移行支援は、一般企業への就職を目指す障害のある方が、就職に必要なスキルやコミュニケーション能力を身につけるための訓練を受けられる福祉サービスです。原則として障害者手帳が必要ですが、自治体によっては医師の診断書や意見書で利用できる場合もあります。
就労移行支援事業所では、パソコンスキルやビジネスマナーの訓練、模擬就労、企業実習などを通じて、実践的な就労準備を行います。また、就職活動のサポートや、就職後の定着支援も受けられるため、安心して就職に臨めます。
利用期間は原則2年間で、利用料は前年の世帯収入に応じて決まりますが、多くの方は無料または低額で利用できます。
就労定着支援
就労定着支援は、就職後6か月を経過した方が、最長3年間にわたって職場定着のための支援を受けられる制度です。月1回以上、支援員が職場や自宅を訪問し、仕事上の悩みや生活面での困りごとについて相談に乗ってくれます。
職場の上司や同僚との関係調整、業務内容の見直し、生活リズムの管理など、働き続けるために必要な様々なサポートを受けられます。この制度があることで、就職後の不安を軽減し、長期的な就労継続が可能になります。
障害者就業・生活支援センター
全国に設置されている障害者就業・生活支援センターでは、就職に関する相談から、就労後の職場定着支援、生活面での相談まで、総合的なサポートを受けられます。
ハローワークや企業、福祉機関などと連携しながら、一人ひとりに合わせた支援計画を立て、長期的にサポートしてくれます。相談は無料で、手帳を持っていれば誰でも利用できます。
各種助成金や公共サービスの減免
障害者手帳を持つことで、税金の控除、交通機関の運賃割引、公共施設の利用料減免など、経済的な支援も受けられます。これらは就労に直接関係するものではありませんが、生活全体の負担を軽減することで、働きやすい環境づくりにつながります。
手帳は返納できる?更新や有効期限について
障害者手帳の取得を躊躇する理由の一つに、「一度取ったら一生持ち続けなければならないのでは」という不安があります。しかし、実際には手帳は必要に応じて返納することができます。
手帳の種類による違い
身体障害者手帳には基本的に有効期限がありませんが、障害の状態が改善した場合は、自治体に返納することができます。ただし、障害の程度によっては、定期的な再認定が必要なケースもあります。
療育手帳(知的障害)は、自治体によって異なりますが、多くの場合、数年ごとに更新が必要です。成人後も状態に応じて更新の可否が判断されます。
精神障害者保健福祉手帳には有効期限があり、2年ごとに更新が必要です。更新時に診断書を提出し、医師が「手帳の交付要件を満たさなくなった」と判断すれば、更新されずに手帳は失効します。
返納のタイミング
手帳は、自分が必要ないと判断したときに、いつでも返納できます。症状が改善して配慮が不要になった、一般雇用枠に転職することにした、などの理由で返納する方もいます。
返納手続きは、居住地の自治体窓口で行います。手帳を返納すると、障害者雇用枠での就労は継続できなくなるため、タイミングには注意が必要です。
再取得も可能
一度返納しても、再び症状が悪化したり、配慮が必要になったりした場合は、改めて申請して手帳を取得できます。手帳の取得と返納を人生の状況に応じて柔軟に選択できることを知っておくと、取得へのハードルが下がるかもしれません。
取得を悩んでいる方が相談できる場所
障害者手帳を取るべきか、障害者雇用を選ぶべきか、一人で悩んでいても答えは出にくいものです。専門家や経験豊富な相談員に話を聞いてもらうことで、自分に合った選択が見えてくることもあります。
公共職業安定所の専門窓口を活用する
ハローワーク(公共職業安定所)には、障害者の就職支援を専門に行う窓口があります。「専門援助部門」や「障害者窓口」と呼ばれることが多く、障害者雇用に詳しい相談員が対応してくれます。
ハローワークでは、障害者雇用枠の求人情報を検索できるだけでなく、手帳取得に関する情報提供や、どのような働き方が自分に合っているかのアドバイスも受けられます。また、一般雇用枠と障害者雇用枠の両方の求人を比較しながら、自分に最適な選択を考えることもできます。
相談は無料で、予約なしでも対応してもらえますが、じっくり話を聞いてほしい場合は事前予約がおすすめです。手帳がなくても相談できるので、気軽に足を運んでみるとよいでしょう。
地域の保健・福祉センターに相談する
精神保健福祉センターや保健所、市区町村の障害福祉課でも、手帳取得に関する相談ができます。これらの機関では、手帳の申請手続きについて詳しく教えてもらえるだけでなく、取得後に利用できる福祉サービスについても情報提供してくれます。
特に精神保健福祉センターでは、精神科医や精神保健福祉士などの専門スタッフが、障害の受容から社会復帰まで、幅広い相談に応じています。手帳を取ることへの不安や葛藤についても、じっくり話を聞いてもらえます。
また、保健師による家庭訪問や電話相談を行っている自治体もあります。外出が難しい場合や、対面での相談に抵抗がある場合は、こうしたサービスの利用も検討してみてください。
就労訓練サービスで専門家に相談する
就労移行支援事業所の多くは、利用前の見学や相談を受け付けています。手帳がなくても見学や相談は可能なので、実際に事業所を訪れて、どんな訓練をしているのか、どんな人が利用しているのかを見てみるのもよいでしょう。
就労移行支援事業所には、就労支援の専門知識を持つスタッフが在籍しています。手帳を取るべきか迷っている状況を伝えれば、これまでの支援経験に基づいた具体的なアドバイスをもらえます。
また、事業所によっては、手帳取得前でも体験利用を受け入れているところもあります。実際に訓練を体験してみることで、障害者雇用で働くイメージが具体的になり、手帳取得の判断材料になるかもしれません。
障害者雇用における職務内容の実態
「障害者雇用枠では、どんな仕事ができるのか」というのは、就職を検討する上で重要な関心事です。ここでは、実際にどのような職種があるのか、キャリアアップの可能性はあるのかについて見ていきましょう。
実際に募集されている業務の種類
障害者雇用枠の求人は、事務系の職種が中心ですが、それ以外にも様々な業務があります。
事務・データ入力
最も多いのが、一般事務やデータ入力の仕事です。書類整理、データ入力、ファイリング、郵便物の仕分けなど、定型的な業務が中心となります。パソコンの基本操作ができれば応募できる求人が多く、未経験者でもチャレンジしやすい職種です。
近年では、単純作業だけでなく、経理補助や総務補助、営業事務など、専門性のある事務職の求人も増えています。
軽作業・製造補助
工場や物流センターでの軽作業、製品の検品、梱包、ピッキングなどの仕事もあります。立ち仕事や体を動かす仕事が好きな方に向いています。
製造業では、部品の組み立てや検査など、技術を身につけられる仕事もあります。手先の器用さや集中力を活かせる職種です。
清掃・施設管理
オフィスビルや商業施設、公共施設などでの清掃業務も、障害者雇用で多く見られる職種です。一人で黙々と作業できるため、人とのコミュニケーションに不安がある方にも向いています。
IT・プログラミング
近年増えているのが、IT系の専門職です。ウェブデザイン、プログラミング、システム運用、データ分析など、専門スキルを活かせる求人があります。在宅勤務やフレックス制度を導入している企業も多く、障害特性に応じた柔軟な働き方がしやすい職種です。
サービス業
小売店や飲食店、ホテルなどのサービス業でも、障害者雇用枠の求人があります。接客業務だけでなく、バックヤードでの調理補助、商品管理、予約管理などの仕事もあります。
クリエイティブ職
デザイナー、イラストレーター、ライター、動画編集者など、クリエイティブな仕事も選択肢に入ります。フリーランスとして活動している方もいますが、企業の障害者雇用枠で正社員として働くケースも増えています。
正規雇用を目指すことは可能か
障害者雇用枠での採用は、契約社員やアルバイトからスタートするケースが多いですが、正社員登用の道が用意されている企業も増えています。
段階的なステップアップ
多くの企業では、まず短時間勤務や契約社員として働き始め、業務に慣れてきたら徐々に勤務時間を延ばしたり、業務範囲を広げたりする方式を取っています。一定期間働いて実績を積み、体調も安定していることが確認できれば、正社員登用の選考を受けられます。
このような段階的なアプローチは、企業にとっても本人にとっても、ミスマッチを防ぎながら長期的な雇用関係を築ける方法として評価されています。
評価制度の整備
障害者雇用に力を入れている企業では、障害者雇用枠の社員にも明確な評価制度やキャリアパスを設けています。目標設定と評価面談を定期的に行い、能力や成果に応じて昇給や昇格が行われます。
障害の有無に関わらず、スキルと実績で評価する文化が定着している企業では、障害者雇用枠から管理職やリーダーになった事例もあります。
専門性を高める
特に専門スキルが求められる職種では、障害者雇用枠であっても、一般雇用枠と同等の待遇やキャリアアップの機会があります。IT系の技術職や、会計・法務などの専門職では、資格取得やスキルアップを支援する制度を用意している企業もあります。
自分の専門性を高め続けることで、長期的なキャリア形成が可能になります。
手帳取得の具体的な手順と準備
障害者手帳を取得すると決めた場合、どのような手続きが必要なのか、事前に流れを把握しておくとスムーズです。
基本的な申請の流れ
- かかりつけの医師に相談し、診断書を作成してもらう
- 居住地の市区町村窓口で申請書類を入手する
- 申請書、診断書、顔写真、マイナンバーカードなどを提出する
- 審査が行われる(自治体によっては、認定調査や医師の面談がある)
- 手帳が交付される
手帳の種類による違い
身体障害者手帳は、身体障害者福祉法に定められた障害に該当する必要があります。視覚、聴覚、肢体不自由、内部障害などが対象で、障害の程度により1級から6級に区分されます。
療育手帳は、知的障害のある方が対象です。自治体によって名称が異なり(愛の手帳、緑の手帳など)、判定基準も若干異なります。児童相談所や知的障害者更生相談所での判定が必要です。
精神障害者保健福祉手帳は、精神疾患により長期にわたり日常生活や社会生活に制約がある方が対象です。統合失調症、うつ病、双極性障害、てんかん、発達障害、高次脳機能障害などが含まれます。初診から6か月以上経過していることが申請の条件です。
申請から交付までの期間と必要経費
交付までの期間
申請から手帳が交付されるまでの期間は、自治体や手帳の種類によって異なりますが、おおむね1か月から3か月程度かかります。
精神障害者保健福祉手帳は比較的早く、1~2か月程度で交付されることが多いです。身体障害者手帳や療育手帳は、認定調査や判定に時間がかかるため、2~3か月かかることもあります。
就職活動のスケジュールを考えている場合は、余裕を持って早めに申請することをおすすめします。
費用について
障害者手帳の申請自体に手数料はかかりません。ただし、診断書の作成には医療機関によって費用が発生します。
診断書の料金は医療機関によって異なりますが、一般的には3,000円から10,000円程度です。精神科の診断書は比較的高額になる傾向があります。
また、申請時に顔写真(縦4cm×横3cm)が必要です。写真館で撮影する場合は1,000円前後、証明写真機なら数百円程度かかります。
生活保護を受給している方や、一定の要件を満たす方は、診断書料の助成制度がある自治体もあるので、事前に確認してみてください。
よくある質問:障害者雇用と手帳について
障害者雇用や手帳取得を検討する際に、多くの方が抱く疑問や不安について、具体的にお答えします。
手帳を取ると、今後に不利になることはありますか?
「手帳を取ることで、将来的に不利益を被るのではないか」という不安を持つ方は少なくありません。しかし、基本的に手帳を持っていることで法的に不利益を受けることはありません。
手帳の情報は個人情報として保護されており、本人が開示しない限り、他人に知られることはありません。就職活動で障害を開示するかどうかは本人の自由です。一般雇用枠に応募する場合、手帳を持っていることを伝える義務はありません。
一部に、保険加入や資格取得の際に制限があるケースもありますが、これは手帳の有無ではなく、障害や疾患の状態そのものによる制限です。手帳を持つことで新たに制限が生じるわけではありません。
むしろ、手帳を持つことで利用できる支援制度やサービスが増え、生活や就労の選択肢が広がるというメリットのほうが大きいと言えます。
手帳なしでできる仕事や制度はありますか?
手帳がなくても利用できる支援制度や働き方はあります。
ハローワークの一般相談
手帳がなくても、ハローワークで就職相談を受けることができます。障害があることを伝えれば、担当者が配慮を要する求人を一緒に探してくれることもあります。
地域若者サポートステーション
15歳から49歳までの就労に困難を抱える若者を支援する機関です。手帳の有無に関わらず、就労に向けた相談や訓練を受けられます。
就労準備支援事業
生活困窮者自立支援制度の一環として、就労に向けた準備が必要な方を支援する事業です。手帳がなくても、自治体の判断で利用できる場合があります。
一般雇用枠での就職
手帳がなくても、一般雇用枠での就職は可能です。企業によっては、障害があることを開示した上で、配慮を受けながら働ける環境を整えてくれるところもあります。
どこに相談すれば適切なアドバイスがもらえる?
手帳取得や障害者雇用について相談できる窓口は複数あります。自分の状況に応じて、適切な相談先を選びましょう。
医療機関
まずはかかりつけの医師に相談するのが基本です。手帳取得の要件を満たしているか、どのような配慮があれば働けるかなど、医学的な観点からアドバイスをもらえます。
ハローワーク
就職に関する具体的な相談はハローワークが適しています。求人情報を見ながら、障害者雇用枠と一般雇用枠のどちらが自分に合っているか考えることができます。
障害者就業・生活支援センター
就労と生活の両面から総合的な相談に乗ってくれます。地域の支援機関とのネットワークがあるため、自分に合った支援につなげてもらえます。
就労移行支援事業所
具体的な就労準備を始めたい場合は、就労移行支援事業所に相談するのがよいでしょう。見学や体験を通じて、自分に合った働き方を見つけるサポートをしてもらえます。
ピアサポート団体
同じような経験を持つ当事者から話を聞きたい場合は、障害者の就労を支援する当事者団体やピアサポートグループに参加してみるのもよいでしょう。実体験に基づいたアドバイスが得られます。
特化型転職エージェント
障害者の求人に特化した転職エージェントでは、専門的な知識のあるアドバイザーが在籍しておりアドバイスを受けることができます。もちろん転職や就職を希望する場合には求人の提案から入社までの間のサポートが受けられます。ただしタイミングによっては紹介できる求人がないこともあり、注意が必要です。
障害のある方向けの転職サービスについては、以下の記事が参考になります。
- 「障害者向けおすすめ転職エージェント12選!条件別のおすすめもご紹介」
- 「適応障害のある方向けのおすすめ転職エージェント15選!特徴も比較・解説」
- 「ADHDの方におすすめの転職エージェント17選!オープン向け、クローズもOKの両方をご紹介」
- 「発達障害者向けおすすめ転職エージェント12+3選!オープン・クローズ・グレーゾーンすべて解説」
みんなが使っている転職サービス上位5選 【1,382人に聞いた転職サービス利用状況】
実際に登録したことのある転職サービスについてアンケートをとりました。アンケート結果として、みんなが使っている転職サービスの上位5サービスは以下です。
- 1位|リクルートエージェント(821人)
- 2位|doda(564人)
- 3位|リクナビNEXT(389人)
- 4位|マイナビ転職AGENT(312人)
- 5位|ビズリーチ(288人)
※転職サービスの利用アンケート(クラウドワークス) 回答数:1,382 / 集計期間:2024年09月19日~10月03日
1位|リクルートエージェント(利用回答数:821人) 圧倒的な求人数
「リクルートエージェント」は、求人数、安定したサービス品質で、まずは登録が必須のエージェントです。
まず何と言っても求人数が多いことがおすすめの理由として挙げられます。転職成功の実績も多く、優れているのは求人の数だけではありません。業界に精通したアドバイザーが在籍しているので、ぴったりの求人を見つけ出してくれます。求人やサービスの質・量ともにトップクラスで転職エージェントとしては定番・王道のサービスです。
営業・技術系を中心にあらゆる業種・職種をカバー。総合型ながら条件ごとに特化したページもあり、使いやすいのも人気の理由です。
- リクルートエージェントのおすすめポイント
- 求人数が圧倒的に多い
- 業界に精通したアドバイザーが在籍
- 条件ごとに特化したページがあり使いやすい
基本データ
| リクルートエージェント | |
|---|---|
| 求人数 | 公開求人数:75万件以上 ※2025年12月2日時点 非公開求人数:35万件以上 ※2025年3月31日時点 |
| 提供サービス | エージェントサービス、提出書類の添削、面接対策、独自に分析した業界・企業情報の提供 |
| 拠点 | 東京・北海道・宮城・宇都宮・さいたま・千葉・横浜・金沢・新潟・長野・静岡・名古屋・京都・大阪・神戸・岡山・広島・高松・福岡 |
| URL | https://www.r-agent.com/ |
2位|doda(利用回答数:564人) エージェント/サイトの一体型で自分でも応募が可能
「doda」は、人材紹介・転職支援を行う大手「パーソルキャリア」が運営する総合型転職サイトです。エージェントサービスも利用できる点が人気の理由の1つになっています。
dodaも求人数が多く、非公開求人も条件が良いものが多いのが大きなポイントです。
また転職サイトと転職エージェントの一体型で、使い方の自由度が高いのもおすすめポイント。エージェントサービスでは専任のキャリアアドバイザーがサポートしてくれます。なお企業との対応は採用プロジェクト担当が行い、求職者と企業とでそれぞれ別のプロフェッショナルが対応します。
- dodaのおすすめポイント
- 非公開求人も好条件多数
- 転職サイトと転職エージェントの一体型で自由度が高い
- 専任のキャリアアドバイザーがサポート、企業は別のプロフェッショナルが対応
基本データ
| doda | |
|---|---|
| 求人数 | 公開求人262,342件/非公開求人31.049件(2024年10月22日現在) |
| 提供サービス | スカウトサービス、年収査定、合格診断、レジュメビルダー、「自己PR」発掘診断、転職タイプ診断、はたらく女性のためのモヤモヤ解消診断、オンライン仕事力診断 |
| 拠点 | 東京・横浜・札幌・仙台・静岡・名古屋・大阪・京都・神戸・岡山・広島・福岡・鹿児島 |
| URL | https://doda.jp/consultant/ |
3位|リクナビNEXT(利用回答数:389人) 求人サイト群の中でも最大級の求人数と使いやすさ
「リクナビNEXT」は大定番の転職サイトで、サイトの見やすさや使いやすさにも定評があります。
エージェントなしの狭義の転職サイトの中では、求人数はトップクラス。新規の求人も多く、定期的にチェックすることで希望に合う求人に出会える可能性が高まります。
ツールが便利でサイトが使いやすいのも特長です。たとえば「気になるリスト」を使うと、気になる企業や後でゆっくりチェックしたい企業をリスト化できるほか、気になるに追加した企業から面接のオファーが来る可能性があります。
そのほか、公開求人・非公開求人の企業からオファーがもらえる「オファーを待つ」、自己分析ツール「グッドポイント診断」などがあります。
- リクナビNEXTのおすすめポイント
- サイトが見やすく使いやすい
- 狭義の転職サイトでは最大級の求人数
- 多くの人が利用している定番の転職サイト
基本データ
| リクナビNEXT | |
|---|---|
| 求人数 | 公開求人824,000件以上(2024年10月22日現在) |
| 提供サービス | オファー、気になるリスト、グッドポイント診断 |
| URL | https://next.rikunabi.com/ |
4位|マイナビ転職AGENT(利用回答数:312人) 20代・30代の求人に強い
「マイナビ転職AGENT」は、さまざまな転職サイトを運営している株式会社マイナビによる転職エージェントです。きめ細かいサポートが受けられると評価されています。
とくに20代・30代の求人が多いので、その世代の人にはおすすめです。また全国に拠点があり地方の求人も充実しているので、大都市圏以外で探している人にもぴったりです。
履歴書や職務経歴書のサポートも充実、初めての転職でも安心して利用できます。IT、営業など業種・職種別のサービスもあります。自分が探している業種と一致するならより探しやすくなるでしょう。
- マイナビ転職AGENTのおすすめポイント
- 20代・30代の求人が多い
- 地方の求人も充実
- 履歴書や職務経歴書のサポートもあり安心
基本データ
| マイナビ転職AGENT | |
|---|---|
| 公開求人数 | 非公開 |
| 提供サービス | エージェントサービス |
| 拠点 | 拠点情報はこちらをご確認ください |
| URL | https://mynavi-agent.jp/ |
5位|ビズリーチ(利用回答数:288人) ハイクラス向けで企業からスカウトが受けられる
「ビズリーチ」は、ハイクラス求人が多いのが特徴の転職サイトです。厳密にはスカウト型のサイトで、エージェントではありません。登録するとヘッドハンターや企業からのスカウトが受けられます。
最大の特長は、ハイクラス求人が多いことです。年収1,000万円以上の求人が1/3以上を占めています。一定以上の経験やスキルがある人が転職活動するのに役立つサービスです。
もう1つの大きな特徴として、登録するだけでヘッドハンターや企業からスカウトが届く点があります。以前は「スカウト」と「プラチナスカウト」の2種がありましたが、今は「プラチナスカウト」に一本化されています。プラチナスカウト経由での採用は全体の約70%。採用される可能性が高く、スカウトが届いたら大きなチャンスです。実際、企業からスカウトが届いた場合は書類選考が免除されます。
基本的にヘッドハンターはアドバイスをしませんが、場合によってはアドバイスをもらえることもあります。無料プランと有料プランがあり、有料プランは制限なく求人に応募できます。
- ビズリーチのおすすめポイント
- ヘッドハンターや企業からのスカウトが受けられるハイクラス向けサイト
- 企業からプラチナスカウトが来た場合は即面接が可能
- 有料プランなら制限なく求人に応募できる
基本データ
| ビズリーチ | |
|---|---|
| 求人数 | 公開求人138,081件(2024年10月22日現在) |
| 提供サービス | スカウトサービス、有料プラン(プレミアムステージ) |
| 拠点 | 東京・大阪・名古屋・福岡・静岡・広島 |
| URL | https://www.bizreach.jp/ |
2026年最新!イチ押しの転職エージェント5選
ここでは、2026年最新のおすすめ転職エージェント5社を厳選してご紹介します。
それぞれの強みや特徴を比較しながら、自分に合ったサービスを見つけ、理想のキャリアへの一歩を踏み出しましょう。
- CAREER-X(キャリア・エックス)
- マイナビクリエイター
- LIG Agent
- Tech-Go(テックゴー)
- エンジニアファクトリー
CAREER-X(キャリア・エックス) 納得のいくキャリアづくりをサポート
「CAREER-X(キャリア・エックス)」は、20代、30代のハイクラス転職に特化した転職エージェントです。
最大の特徴は、納得のいくキャリアを歩むために目の前の転職活動に留まらず、その先のキャリアに伴走すること。キャリアコーチング実績は5,000人以上で、その経験で培ったノウハウをもとに求職者の強みや将来像に合った最適な選択肢をご提案します。
寄り添った面談で強みや挑戦したいことを引き出し、求職者の経験や希望にマッチした求人をご紹介。また、20代で年収700万や30代で経営幹部ポジションなど、ハイクラスの求人や非公開求人も多数保有しています。
また、書類作成と添削、面接対策を内定・入社まで徹底サポート。転職後もフォロー/振り返りを行っており、長期に渡ってキャリアづくりを支援してくれる強い味方です。
- CAREER-X(キャリア・エックス)のおすすめポイント
- ハイクラスの求人や非公開求人も多数保有
- キャリアコーチング実績は5,000人以上
- 長期に渡ってキャリアづくりを支援
基本データ
| CAREER-X(キャリア・エックス) | |
|---|---|
| 求人数 | 非公開 |
| 提供サービス | 職務経歴書の作成と添削、面接対策、入社後フォロー |
| 拠点 | 大阪・福岡 |
| URL | https://career-x.co.jp/ |
マイナビクリエイター 専任のキャリアアドバイザーが直接サポート
「マイナビクリエイター」は、Web・ゲーム・IT業界専門の転職エージェントです。専任のキャリアアドバイザーが個別カウンセリングを行い、求職者のスキルや経験、希望、適性に合った求人をご紹介します。
また、Web・ゲーム・IT業界出身のキャリアアドバイザーが在籍しているのが強みの一つ。企業が求めるクオリティを把握しながら、正確なポートフォリオの作成を徹底サポートします。
さらに、書類添削や面接対策、企業とのやり取り代行も無料で行い、効率よく転職活動ができるよう支援。アドバイザーとのキャリアカウンセリング時間も十分にとれるよう心掛けており、求職者と真摯に向き合う対応力が魅力といえるでしょう。
- マイナビクリエイターのおすすめポイント
- Web・ゲーム・IT業界出身のキャリアアドバイザーが在籍
- 正確なポートフォリオの作成を徹底サポート
- 書類添削や面接対策、企業とのやり取り代行も無料で行う
基本データ
| マイナビクリエイター | |
|---|---|
| 求人数 | 非公開 |
| 提供サービス | 求人紹介、書類添削、面接日程の調整、面接対策、入社日の調整、条件面の交渉、入社日までのフォロー |
| 拠点 | 要確認 |
| URL | https://mynavi-creator.jp |
LIG Agent 活躍の幅を広げる多種多様な求人多数
「LIG Agent」は、クリエイティブ業界で20年の実績を持つ「LIG」が運営するクリエイターのための転職エージェントです。クリエイティブ業界に特化しているからこそ、豊富な知識や最新トレンド、実践的な情報などを惜しみなく提供。
非公開求人を含む多様な業界・職種のクリエイティブ・IT分野の求人を多数保有!求職者の経験やスキル、キャリアステージ、希望の働き方に合った求人をご紹介します。
また、年間1,000名以上のキャリアサポート実績あり。ポートフォリオや職務経歴書の添削、面接対策から入社後のフォローまで一貫して転職活動を徹底的に支援します。
さらに、今後のキャリア設計も一緒に検討してご提案します。クリエイターがスキルと経験を最大限に活かし、理想のキャリアを築ける心強い味方になってくれるはずです。
- LIG Agentのおすすめポイント
- 非公開求人を含む多様な業界・職種の求人を多数保有
- 年間1,000名以上のキャリアサポート実績あり
- 添削、面接対策から入社後のフォローまで一貫してサポート
基本データ
| LIG Agent | |
|---|---|
| 求人数 | 678件(2026年2月17日現在) |
| 提供サービス | キャリア相談、求人紹介、面接対応、書類・ポートフォリオ添削、業界トレンド共有、イベント・セミナー実施 |
| 拠点 | 東京・広島・セブ・ベトナム |
| URL | https://re-new.liginc.co.jp/ |
Tech-Go(テックゴー) エンジニア経験を活かしキャリアアップを実現
「Tech-Go(テックゴー)」は、ITエンジニアの転職支援に特化した転職エージェントです。
ITエンジニア向けの求人を10,000件以上保有。取り扱っている求人は幅広く、「Tech-Go(テックゴー)」だけの独占選考ルートや面接確約求人など、他にはない求人が多数揃っています。
また、現場を知り尽くしたエンジニア業界出身のアドバイザーが在籍しており、選考通過率をアップする書類添削や独自の面接対策など、転職活動を徹底サポートします。
さらに、年収アップを実現する交渉力も強みの一つ。エンジニアとしてキャリアアップを実現し、年収アップを目指している方におすすめの転職エージェントといえます。
- Tech-Go(テックゴー)のおすすめポイント
- ITエンジニア向けの求人を10,000件以上保有
- 現場を知り尽くしたエンジニア業界出身のアドバイザーが在籍
- 年収アップを実現する交渉力も強み
基本データ
| Tech-Go(テックゴー) | |
|---|---|
| 求人数 | 非公開 |
| 提供サービス | 求人紹介、キャリア相談、書類添削、面接対策、日程調整、条件交渉 |
| 拠点 | 東京 |
| URL | https://tech-go.jp/ |
エンジニアファクトリー フリーランスエンジニアの強い味方!
「エンジニアファクトリー」は、18年以上の実績を誇るIT専門フリーランスの転職エージェントです。10,000件以上の求人を保有。会員登録をすれば非公開案件も見ることができ、あなたの経験やスキル、希望にぴったりな求人を見つけることが可能です。
また、年収と再受注率が業界トップクラス!確かな実績があるからこそ、フリーランスとして働いても安心感を得られます。もちろん正社員も対応可能なため、フリーエンジニアとして働いてきた方を、円滑に転職路線に切り替えることができます。
さらに、フリーランス向け福利厚生サービスを設けており、万が一のリスクに備えたサポートが充実している点も魅力の一つです。
- エンジニアファクトリーのおすすめポイント
- 会員登録をすれば非公開求人を見ることができる
- 年収と再受注率が業界トップクラス
- フリーランス向け福利厚生サービスが充実している
基本データ
| エンジニアファクトリー | |
|---|---|
| 求人数 | 12,450件(2026年2月17日現在) |
| 提供サービス | 案件紹介、企業面談、企業との契約 |
| 拠点 | 東京・大阪 |
| URL | https://www.engineer-factory.com/ |
まとめ:自分に合った働き方を見つけるために
障害者雇用枠に応募するには、原則として障害者手帳が必要です。手帳がない場合は、一般雇用枠での就職活動を行うか、手帳取得を検討することになります。
手帳を取得することで、障害者雇用枠への応募が可能になり、法的に保障された配慮を受けながら働けるようになります。また、就労移行支援や就労定着支援など、様々な支援制度も利用できるようになります。一方で、「障害者」として働くことへの心理的な抵抗や、求人の選択肢が限られるといったデメリットもあります。
手帳取得は、一度取ったら一生持ち続けなければならないものではありません。状況に応じて返納することもできますし、必要になったら再取得することも可能です。あまり構えすぎず、今の自分にとって何が必要かという視点で考えてみてください。
重要なのは、「手帳を取るべきか」という二択で考えるのではなく、「自分がどう働きたいか」「どんな配慮があれば能力を発揮できるか」という視点で考えることです。
まずは専門機関に相談し、情報を集めることから始めてみてください。ハローワーク、保健所、就労移行支援事業所など、様々な相談先があります。一人で抱え込まず、専門家の力を借りながら、自分に合った働き方を見つけていきましょう。
障害があってもなくても、誰もが自分らしく働ける社会の実現に向けて、障害者雇用制度は進化し続けています。あなたが一歩を踏み出すための情報が、この記事から得られたなら幸いです。







.png)


.png)